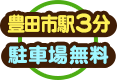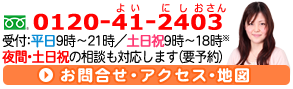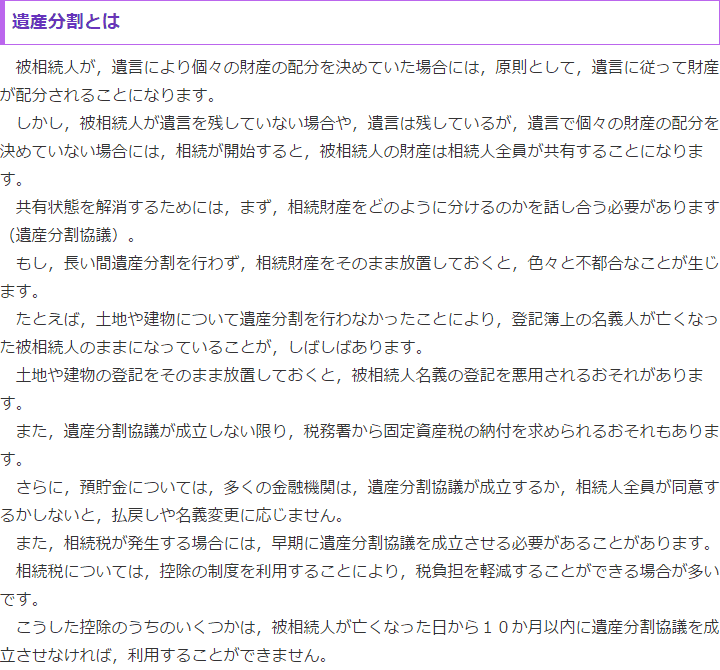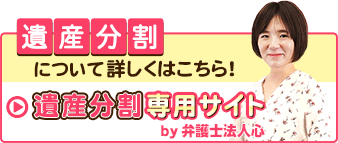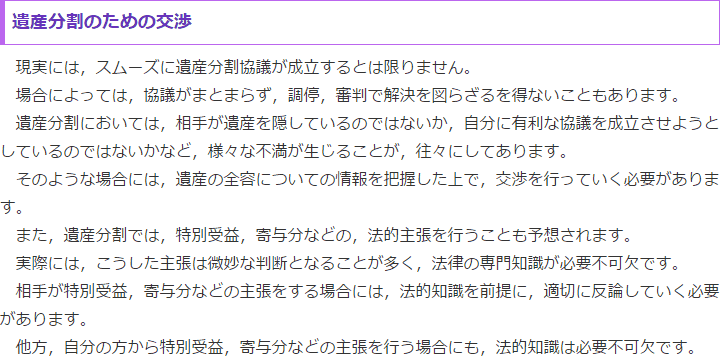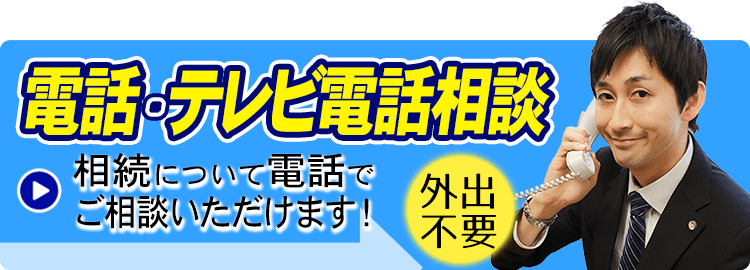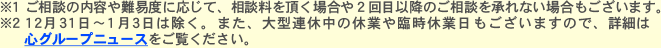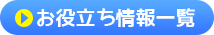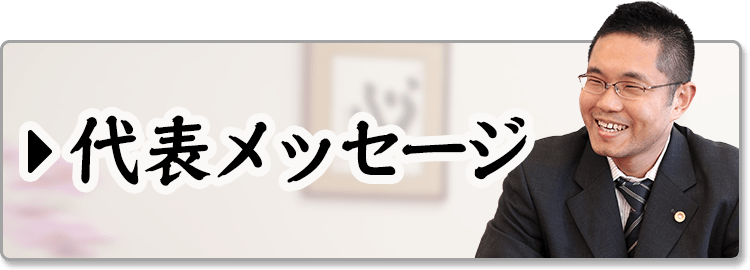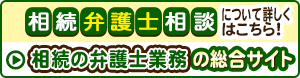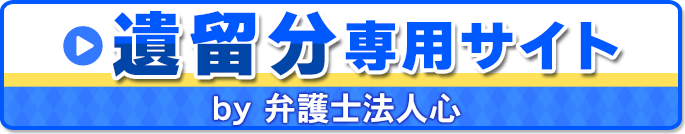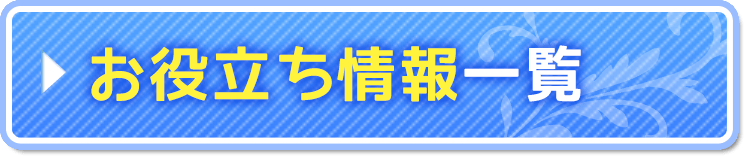遺産分割
来所しやすい便利な立地
最寄り駅から徒歩数分の場所に設けているため、例えば、お仕事帰りに相談にお立ち寄りいただくということもしていただきやすいかと思います。
遺産分割を専門家に依頼した場合の費用
1 紛争性がない場合の費用の目安

相続人同士で揉めていない場合は、相続人同士で決めた遺産分割の内容に従い、名義変更などの手続きを進めていくことになります。
これらの手続きを弁護士や司法書士、行政書士といった専門家に依頼した場合、遺産の内容や相続人の数等によっても大きく異なりますが、おおよそ遺産の0.3%から1%程度(最低30万円程度)の費用がかかることが多いです。
たとえば、遺産が3000万円の場合、相場としては、30万円と税金がかかることが多いです。
もっとも、信託銀行や銀行に遺産分割手続きを依頼した場合、最低でも100万円と税金がかかることが多く、他の専門家に比べて割高になっているのが現状です。
なお、信託銀行や銀行に遺産分割手続きを依頼した場合でも、不動産の名義変更手続きは、別途、司法書士への報酬がかかるため、予想以上に費用がかかる場合があります。
2 遺産分割の紛争を依頼した場合の費用の目安
遺産分割について、相続人間で揉めてしまった場合、弁護士しか代理人になれません(弁護士以外が代理人となることは違法です)。
弁護士の報酬についても、事務所ごとによって大きく異なりますが、着手金として20万円~30万円、報酬金が得られた財産額の10%~15%と税金がかかることが多いです。
なお、着手金について、弁護士事務所の中には、交渉の場合は20万円ですが、調停を行う場合は追加で10万、審判になるとさらに追加で10万円などと、どんどん費用が加算されていく事務所もある一方、着手金がかからないという事務所もあります。
3 遺産分割に付随して相続税を依頼した場合の費用
遺産分割において、相続税がかかる場合は、10か月以内に相続税の申告を行う必要があります。
相続税の申告は、税理士しか代理で行うことができません(税理士以外の専門家が相続税の申告を代理することは違法です)。
遺産分割後の相続税申告についても依頼したいとなると、相続税申告に関する税理士の報酬については、相続人の数や遺産の内容、特に土地や非上場株式の数によっても大きく異なりますが、一般的には、遺産の総額の0.7%から1%前後が多いです。
そのため、遺産が1億円の場合は、税理士報酬として、70万円~100万円と税金がかかることが多いです。
遺産分割について相談すべき専門家
1 遺産分割は専門家選びが極めて重要

どの専門家に遺産分割の相談をするかによって、納める相続税の金額や手続き終了までの期間が変わってくることがあります。
例えば、遺産相続に詳しくない専門家に相談してしまった結果、遺産分割の手続きにトラブルが発生してしまい、相続人間で泥沼の紛争になってしまったり、余分な税金を納めなければならなくなったりする可能性があります。
2 遺産分割に関わる専門家
遺産分割においては、弁護士や税理士、行政書士、不動産会社など、多くの専門家が関わることがあります。
例えば、相続手続きや相続人同士で揉めてしまっている場合は、弁護士に相談した方がよいです。
また、相続税がかかる場合は税理士に、遺産である不動産を売却する場合は不動産会社に相談した方がよいでしょう。
もっとも、同じ専門家とはいえ、得意とする分野がそれぞれ違うため、中には相続に詳しくない方もいらっしゃいます。
もし、そのような専門家に相談してしまうと、満足できる結果にならない可能性もあります。
特に、相続人同士で揉めている場合や相続税が関わってくる場合は、結果が大きく異なることもありますので、注意が必要です。
実際、相続税に詳しくない税理士に相談した結果、誤ったアドバイスを受けてしまい、余分に税金を支払ったケースもあります。
3 相続に強い専門家にご相談を
このように、遺産分割においては多くの専門家が関わってくる半面、専門家の中には相続に詳しくない者もいることから、遺産分割を相談するときには、相談先を慎重に選ぶ必要があります。
おすすめの相談先としては、弁護士や税理士、行政書士や不動産会社など、複数の専門家が連携し、なるべく全ての手続きを一括で任せられる事務所、かつ、遺産相続に詳しい事務所などが挙げられます。
その事務所が相続に詳しいどうかは、専門家の数や、相続に関する専門サイトがあるなどといったホームページの内容、実績等を参考にするとよいかと思います。
遺産分割で失敗しないためにも、相続を得意としており、安心して任せられる事務所に相談されることをおすすめします。
遺産分割協議書を作成する際に注意すること
1 間違えると遺産分割協議書が無効になる場合がある

遺産分割協議書について、作成方法を間違えると、せっかく作った遺産分割協議書が無効になってしまう場合があります。
たとえば、相続人のうち、1人でも欠けた状態で作成された遺産分割協議書は無効になります。
実際、専門家が作成した遺産分割協議書でも、内容に問題があり、トラブルになった事例があります。
以下では、遺産分割協議書が無効にならないためにも、また、後日の無用なトラブルを避けるためにも、遺産分割協議書を作成する際の注意点について説明します。
2 相続人の一部が欠けて作成された遺産分割協議書
相続人のうち、一人でも、遺産分割協議に参加せずに作成された遺産分割協議書は無効です。
よくある実例として、被相続人に前妻(前夫)との間に子がいたケースや、認知された隠し子がいたケースなどがあります。
また、被相続人の相続人が兄弟姉妹の場合、異父兄弟や異母兄弟がいたというケースもあります。
相続人の一部が欠けた状態で遺産分割協議書が作成されてしまう理由としては、だいたいの場合は十分な相続人調査が行われなかったためです。
基本的に、遺産分割を行うにあたっては、戸籍謄本等で相続人を調査する必要があります。
しかし、「まさか隠し子がいるはずがない」「他に相続人はいないだろう」という先入観から、相続人調査が十分に行われないまま遺産分割が行われ、相続人の一部が欠けた状態で遺産分割協議書が作成されてしまいます。
そのため、遺産分割協議書を作成する場合は、事前に十分な相続人調査を行ったうえで作成する必要があります。
3 重度の認知症や未成年の相続人がいる場合
相続人の中に、重度の認知症の方がいる場合など、判断能力がない方がいる場合、その方に成年後見人等を選任して遺産分割協議書を作成しないと、遺産分割協議書自体が無効になる可能性があります。
なかには、成年後見人等を選任せず、親族が重度の認知症の相続人に代わって遺産分割協議書に署名・押印する場合もあるようですが、遺産分割協議書が無効になるリスクもあるだけでなく、私文書偽造罪等の犯罪に当たる可能性もありますので、おすすめできません。
そのため、重度の認知症で判断能力がない相続人がいる場合は、成年後見人等を選任した上で遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。
また、相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者のために特別代理人を選任して遺産分割を行わないと、遺産分割協議書が無効となってしまう可能性があります。
たとえば父親が亡くなり、親権者である母親と、未成年の子が相続人となったケースにおいて、母親が未成年の子を代理して遺産分割を行うことは、利益相反行為にあたります。
この場合、家庭裁判所に請求して、未成年の子のために特別代理人を選任してもらう必要があります。
4 財産の一部が欠けてしまった場合
遺産分割協議書を作成したものの、財産の一部が欠けていた場合、遺産分割協議書自体が無効になることはありませんが、欠けた財産について、新たに遺産分割協議書を作り直す必要があります。
この点、金融機関の中には、預貯金口座の一部だけ分け方が決まっているが、他の口座の分け方が決まっていない場合、分け方が決まっている預貯金口座であっても、解約に応じてくれないところもありますので、注意が必要です。
このように、財産の一部が欠けて作成された遺産分割協議書だと、後々トラブルになったり、手続が滞ったりすることになりかねません。
そこで、「後日見つかった財産や遺産分割協議書に記載のない財産については、相続人の○○が取得する」といったように、後から見つかった財産への対応方法等についてももれなく書いておくことをおすすめします。
5 記載内容が不正確な場合
遺産分割協議書の記載内容が不正確な場合、預貯金の解約や不動産の名義変更等ができなくなる場合があります。
たとえば、預貯金を記載する場合は、誰の相続について、誰が、どの預貯金口座を取得するのか、預貯金の支店名や口座の種類、口座番号まで細かに書く必要があることもあります。
また、不動産についても、所在や地番、地積等を正確に記載しておかなければなりません。
財産の記載について、誤字や脱字があった場合、名義変更ができなくなってしまう場合があります。
6 まずは専門家にご相談を
このように、遺産分割協議書を作成するにあたっては、様々な注意点が存在します。
これらの点について間違えて作成してしまうと、遺産分割協議書自体が無効になる場合もあります。
また、他にもここでは書ききれなかった注意点(割合で遺産を分ける場合は、必ず端数の取得者も記入するなど)もあります。
遺産分割協議書を作成しようと考えている方は、一度、専門家にご相談されることをおすすめします。