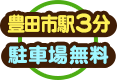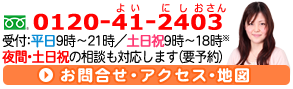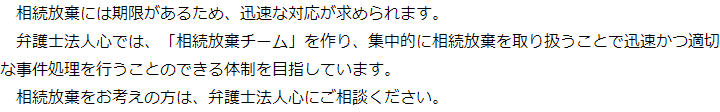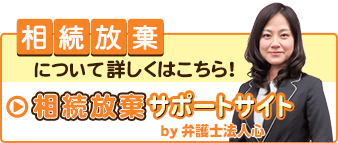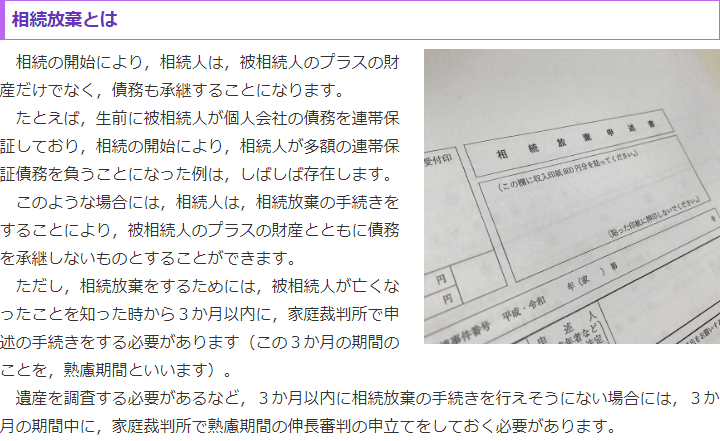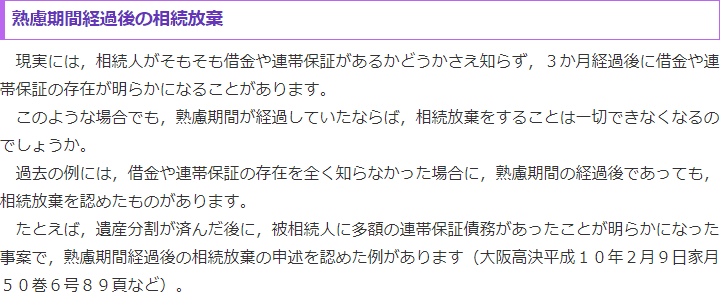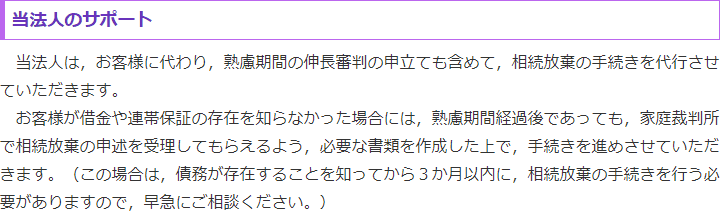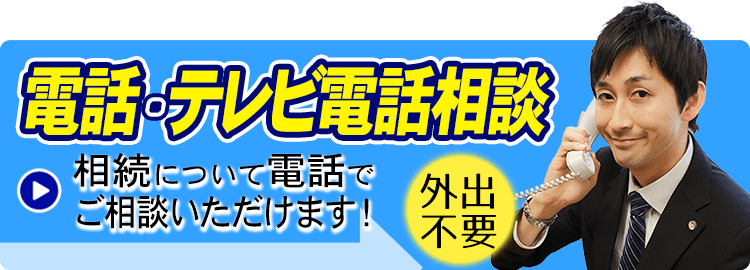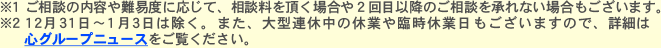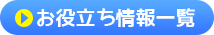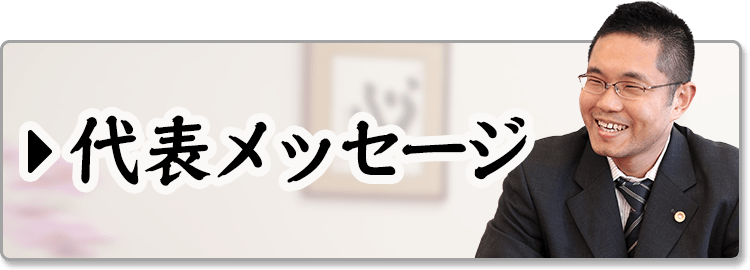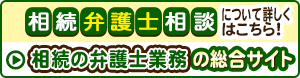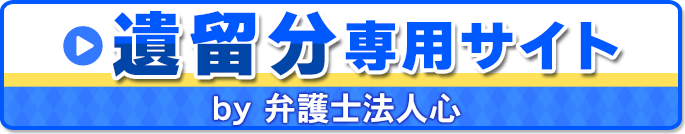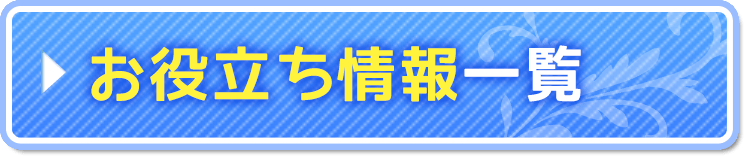相続放棄
ご利用いただきやすい立地です
対面でのご相談の際に、足を運んでいただきやすいように、駅近くの便利な場所に設けています。詳細地図はこちらからご確認いただけます。
相続放棄をした方が良いケース
1 借金が多い場合

亡くなった方(被相続人といいます。)に多額の借金がある場合、相続放棄を3ヶ月以内に行わないと、その借金も背負うことになります。
借金については、基本的に借りた人が亡くなっても、その相続人に承継されるためです。
そのため、預貯金・不動産といったプラスの財産よりも、借金などマイナスの財産が多い場合は、基本的に相続放棄をした方が良いでしょう。
なお、借金があるが、自宅など手放したくない財産がある場合、限定承認という手続きを検討するケースもあります。
詳しくはご相談ください。
2 借金の額がわからない場合
被相続人と長年疎遠であり、借金の額がわからない場合も、相続放棄をした方が安心な場合があります。
被相続人の財産や生活状況がわからなければ、借金や財産がどれだけあるのかが分からないためです。
もちろん、請求書を探したり、信用情報を調べたりすれば、借金についてある程度は判明します。
しかし、個人からの借入や、連帯保証人の責任などについては、調査方法が限られるため、それらすべてを調査することが困難な場合もあります。
そのため、安心を優先するのであれば、相続放棄をした方が良いかも知れません。
3 相続手続きに関わりたくない場合
特に相続したい財産もなく、また、他の相続人とも関わりたくない場合、相続放棄を行えば、相続人と遺産の分配について、話し合いをしなくて済みます。
また、遺産を取得しない場合でも、相続放棄をしないと借金を負う可能性があるため、相続放棄をした方が良いでしょう。
もっとも、注意点として、相続放棄をすることで、残された相続人が遺産分割で困る場合があります。
たとえば、父が亡くなり、相続人が母と子の場合、子が全員相続放棄をすると、相続人は母だけでなく、父の両親や父の兄弟姉妹、甥姪も相続人になります。
そのため、残された母としては、父の親族(父の両親や父の兄弟姉妹、甥姪など)と遺産分割の話合いをしなければならず、手続きがたいへんになる場合があります。
このように、相続放棄を行う場合も、注意点や落とし穴などが多数ございますので、ご不安な場合は、すぐにご相談されることをおすすめします。
相続放棄にかかる費用
1 専門家に依頼する場合の報酬
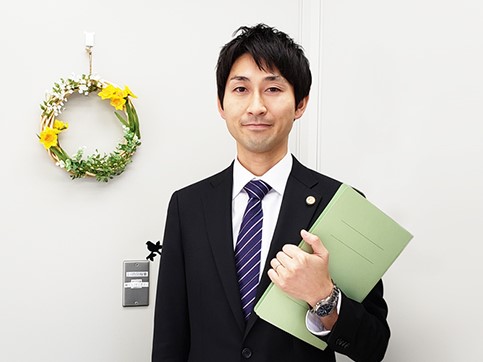
相続放棄を専門家に依頼した場合、専門家に支払う報酬が発生しますが、どの専門家に依頼するかによって、金額が大きく異なってくる場合があります。
おおまかな相場としては、5万円~10万円前後が多いです。
もっとも、事案の内容や相続放棄を行う相続人の人数によって、金額が前後する場合がございますので、詳細は、ご相談される専門家にご確認ください。
なお、専門家と一口にいっても、得意とする分野はその専門家や事務所によって様々です。
相続放棄にあまり詳しくなく、費用は安いけれども適切に手続きを行ってもらえないという事務所も存在するため、費用の安さだけで選んでしまうと、相続放棄でトラブルに発展する可能性もあることには注意が必要です。
2 実費関係
相続放棄を専門家に依頼した場合でも、依頼しなかった場合でも、相続放棄を行う際は、以下のような実費が必要となります。
ア 戸籍謄本や住民票の取得費
相続放棄を行う場合、亡くなった方(被相続人といいます)の住民票または戸籍の附票と戸籍謄本、相続人の戸籍謄本等が必要になります。
相続人が被相続人の甥姪の場合、さらに多くの戸籍謄本が必要となりますので、それらを取得するだけでも1万~2万円程度の実費がかかる場合があります。
戸籍謄本については、市区町村役場で取得することが可能となりますが、その際に450円か750円の費用がかかります。
また、住民票や戸籍の附票についても、市区町村役場で取得することができますが、住民票の取得にかかる費用については、市区町村ごとに異なります。
なお、豊田市の場合は、住民票や戸籍の附票の費用は、150円です。
参考リンク:豊田市・印鑑登録証明書、住民票、戸籍に関する証明書の発行とその手数料
また、本籍地で戸籍謄本を取得しなければならない場合は、郵送でも取得することが可能ですが、その場合は、市区町村役場に支払う費用は定額小為替で納める必要があるため、郵便代の他に定額小為替を購入するための手数料(1枚あたり200円)が必要となります。
なお、定額小為替は、郵便局で購入することができますが、銀行やコンビニでは購入することができませんので、ご注意ください。
イ 裁判所への印紙代
被相続人の住民票や戸籍謄本、相続人の戸籍謄本がそろったら、それらの書類をまとめて裁判所に提出します。
その際、相続放棄を申し立てる相続人1人あたり、800円の収入印紙が必要となります。
収入印紙は、法務局か郵便局等で購入することができ、少額であればコンビニでも購入することができます。
なお、被相続人が複数いる場合は、被相続人の人数分、収入印紙も必要になります。
ウ 切手(郵券)
相続放棄を行う際、切手(郵券)も裁判所に納める必要があります。
切手の金額については、申し立てる裁判所ごとに変わってくるため、事前に、管轄の家庭裁判所に確認しておいた方がよいでしょう。
なお、被相続人の住所地が豊田の場合、名古屋家庭裁判所岡崎支部に申し立てる必要があり、その場合の切手代は、470円分(84円5枚、10円5枚)となります。
切手代については、裁判所が相続人に書類連絡する際に必要になり、余った分は後日、還付されます。
3 相続放棄は専門家にご相談ください
このように、相続放棄を専門家に依頼した場合は、専門家の報酬と実費もあわせると、相続人一人当たり7万円~12万円前後かかる場合が多いです。
他方、ご自身で相続放棄を行う際は、実費しかかかりませんが、確実に相続放棄を行いたい場合は、相続放棄に詳しい専門家にご依頼されることをおすすめします。
万が一、相続放棄が認められないと、被相続人に借金があった場合、その借金も背負うことになり、取り返しのつかない事態に繋がりかねません。
また、相続放棄には厳格な期限があり、相続人が行ってしまうと相続放棄ができなくなる行為もあるなどの注意点があります。
そのような相続放棄の失敗事例については、こちらのページでもご紹介しておりますので、失敗事例について知りたい方はこちらもご確認ください。
以上のことから、より確実に相続放棄をしたいということであれば、相続放棄に詳しい専門家にご相談されたほうがよいでしょう。
相続放棄の方法
1 相続放棄は3か月以内に手続きを行う

相続放棄は、基本的に、被相続人が亡くなったことを知った時から3か月以内に行わなければいけません。
万一、3か月の期間を過ぎてしまった場合、相続放棄ができなくなる可能性がありますので注意が必要です。
なお、相続放棄は、被相続人の負債を引き継がないようにするため相続人間で決断したとしても、裁判所を通して相続放棄の手続きを行う必要があります。
なぜなら、裁判所を通して相続放棄をしないと、債権者に対しては、相続放棄を主張することができないからです。
もし、相続人間の合意等で相続放棄をしたのみで、裁判所での相続放棄の手続きを行わなかった場合、被相続人の借金を負わなければならなくなる可能性がありますので注意が必要です。
2 必要な書類の取得
次に、実際の相続放棄の手続きとしては、以下の必要書類と収入印紙800円分と切手とを、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所へ提出します。
必要書類については、相続放棄をする方と被相続人との関係によって異なってきます。
また、切手の額についても、申し立てる裁判所によって異なりますので、事前に裁判所に確認しておいた方が良いでしょう。
【共通書類】
- ① 相続放棄申述書
- ② 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- ③ 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
【申述人が、被相続人の配偶者の場合】
- ④ 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
【申述人が、被相続人の子又はその代襲者(孫、ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】
- ④ 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ⑤ 申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
【申述人が、被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
- ④ 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本。被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ⑤ 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母))がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
【申述人が、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
- ④ 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ⑤ 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ⑥ 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ⑦ 申述人が代襲相続人(おい、めい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述
3 相続放棄を裁判所に申し立てた後について
裁判所に必要書類等を提出した後、裁判所から照会書が届く場合や、審問が開かれる場合があります。
照会書の内容としては、その相続放棄が申し立てた相続人本人の意思で行われているか、相続放棄ができなくなるようなことを行っていないかを質問されます。
また、審問とは、簡単にいうと、裁判官が直接、相続放棄を申し立てた相続人に対し、詳細を質問することです。
質問の内容としては、相続放棄の意思の確認や、預貯金の解約等の相続放棄ができなくなることを行っていないかを確かめるものです。
照会書が送られてくるケースや、審問が行われるケースだと、照会書への回答や審問等で問題がなければ、相続放棄が認められます。
照会書や審問に問題があった場合、相続放棄が認められない場合がありますので注意が必要です。