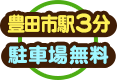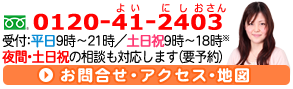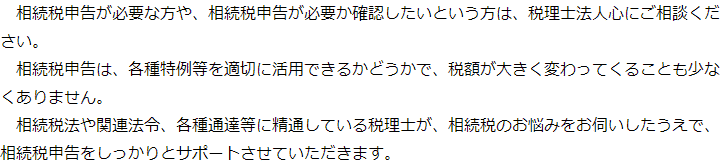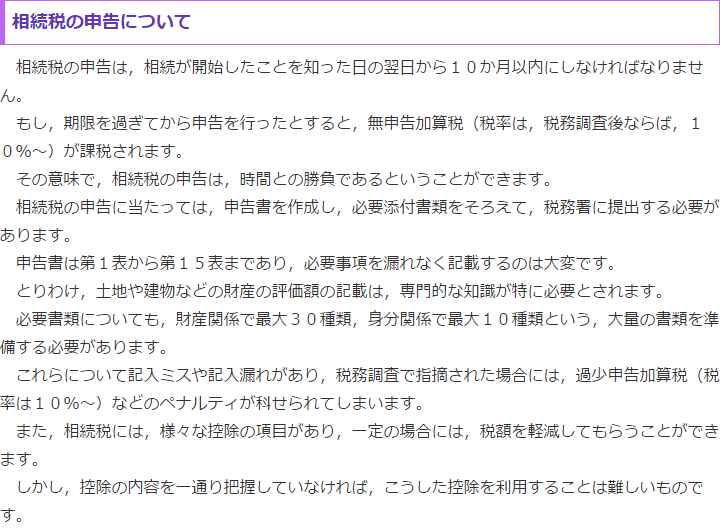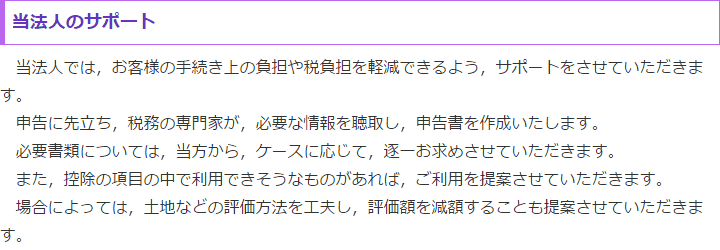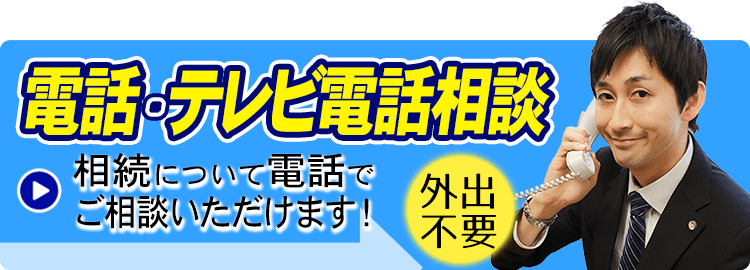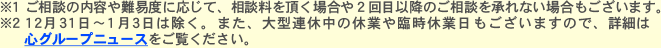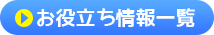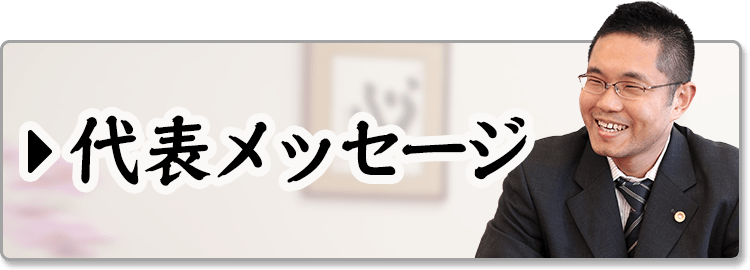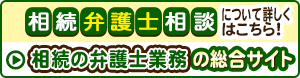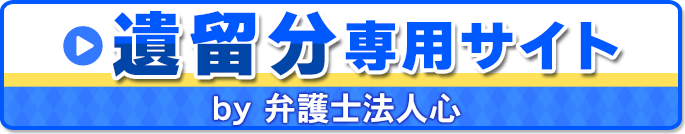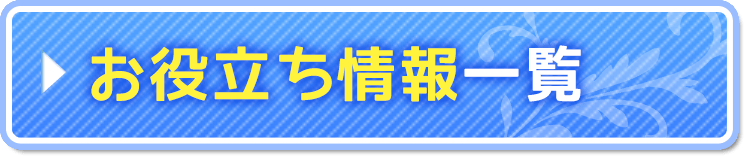相続税申告
便利な立地の事務所です
駅近の立地で、近く又は直結で駐車場のある場所を事務所開設の場所として選んでおります。相続税でお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
相続税の特例にはどのようなものがありますか
1 小規模宅地等の特例

⑴ 小規模宅地等の特例とは
相続税の特例で代表的なものとして、小規模宅地等の特例があります。
この特例は、簡単にいうと、土地の価額を最大80パーセント減額することができる特例です。
たとえば、相続人が子2人で、遺産が土地1億円、建物2000万円のみの場合、小規模宅地等の特例を使わない場合、課税総額は1億2000万円であり、相続税は1160円となります。
他方、小規模宅地等の特例を使うことができれば、土地の価額が2000万円となるため、課税総額は4000万円となり、基礎控除額を超えないため、相続税は0円となります。
このように、小規模宅地等の特例を使えるか否かによって、相続税が大きく異なるため、相続税の申告を行う場合は、優先的に、特例が使えるかどうかを検討した方が良いでしょう。
なお、小規模宅地等の特例の詳細については、以下の国税庁のホームページもあわせてご確認ください。
⑵ 小規模宅地等の特例の種類
小規模宅地等の特例を使える土地の種類としては、3つあります。
①自宅などの住んでいた土地(特定居住用宅地等)、②店舗などの事業をしていた土地(特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等)、③貸駐車場などの貸していた土地(貸付事業用宅地等)です。
小規模宅地等の特例によって、減額される割合については、①~③のどの種類の土地かによっても、50パーセントか80パーセントかで異なります。
①特定居住用宅地等は土地の面積330㎡までの部分について、80パーセント減額され、②特定事業用宅地等は、土地の面積400㎡までについて、80パーセント減額され、③貸付事業用宅地等については、土地の面積200㎡までについて、50パーセント減額されます。
そのため、土地が複数ある場合は、どの土地について、小規模宅地等の特例の特例を使うかによっても、相続税の金額が大きく異なる場合があります。
2 納税猶予の特例(農地等の納税猶予制度)
農地等の納税猶予制度とは、農地を相続した場合、相続税の支払いを先延ばし(もしくは免税)できる特例のことをいいます。
農地等の納税猶予の特例を使うことができるのは、農家を継ぐ方に限り、農業をやめる場合は、利子付きで納税をしなければならないなどのデメリットもあります。
他方、農地を相続した方が、亡くなるまで農家を継続していれば、実質的に、納税猶予された相続税が免除されることになるというメリットもあります。
農地等の納税猶予の特例については、適用できる条件も限られますので、詳細については、以下の国税庁のホームページをご参照いただくか、相続税に詳しい税理士にご相談ください。
※参考リンク:農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例
相続税申告を得意とする税理士に相談するとよい理由
1 どの税理士を選ぶかによって相続税額が変わる場合がある

どの税理士に相続税の申告を依頼するかによって、納める相続税額が異なる場合があります。
実際、相続税に詳しくない税理士に依頼してしまった結果、本来納めるべきはずの額を超えて相続税を納めてしまったという事例も存在します。
なお、相続税を納めすぎたとしても、税務署から自動的に払いすぎた税金が返ってくることはありませんので、注意が必要です。
2 税理士によって相続税の申告額が変わる理由
税理士によって、相続税の申告額が異なる理由として、全ての税理士が相続税に精通しているわけではないということが挙げられます。
相続税に詳しい税理士もいれば、相続税に詳しくない税理士もいます。
実は、税理士の中には、相続税を年間1件ぐらいしか行っていない方や、そもそも相続税を勉強したことがない方がいます。
また、相続税は、土地や株式の評価、特例の適用等を適切に行えるかどうかで、申告額が大きく異なることがあります。
そのため、相続税に詳しくない税理士に依頼してしまうと、土地や株式の評価を間違えてしまう可能性が高くなり、結果として、相続税を多めに納めることになるかもしれません。
3 相続税申告は相続税に強い税理士を
このように、相続税申告については、どの税理士に依頼するかが非常に重要となります。
依頼する税理士を選ぶ際のポイントとして、顧問の税理士や知り合いの税理士という理由だけで決めてしまうのではなく、相続税に強い税理士かどうかで判断することをおすすめします。
相続税に強いかどうかは、その税理士事務所が、年間何件以上の相続税申告に携わっているのか、税理士の人数、事務所の規模等を考慮して、ある程度判断することができます。
あるいは、簡易的な方法として、相続税専門のホームページを作成しているかでも、それなりに判断することができるかと思います。
なぜなら、相続税専門のホームページを作っているということは、それだけ相続税に力を入れている可能性が高いためです。
相続税の申告で後悔することのないよう、相続税を得意とする税理士にご相談ください。