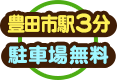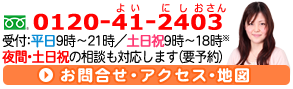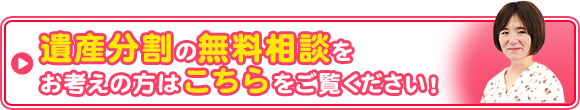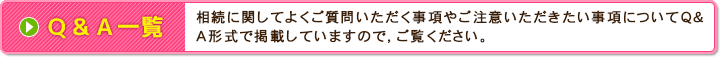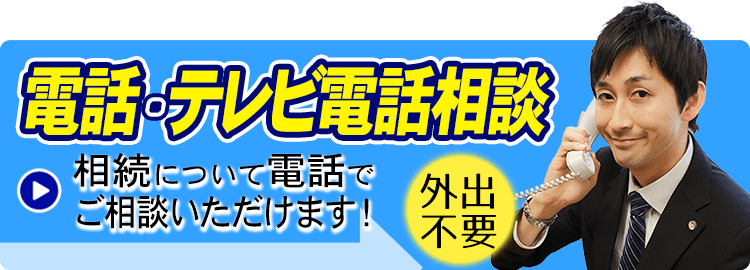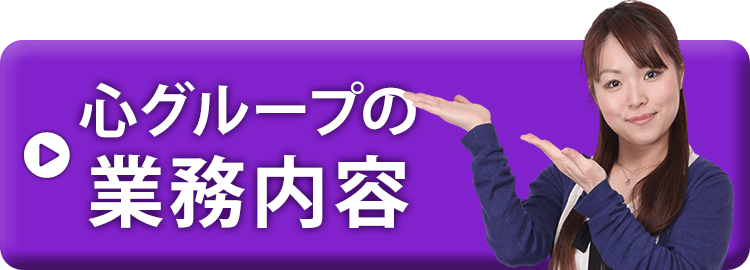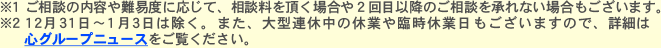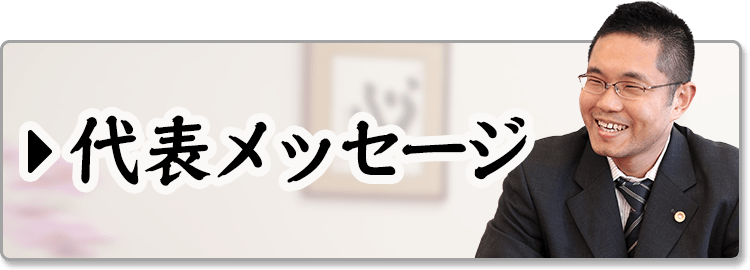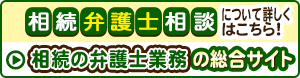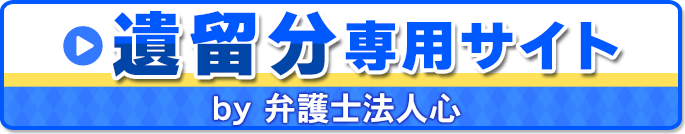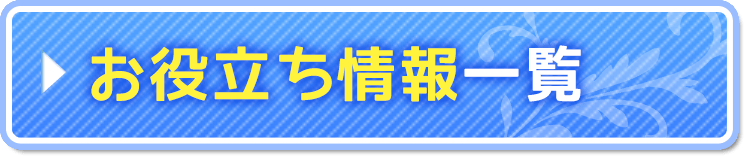遺産分割での葬儀費用の取り扱い
1 葬儀費用の取り扱いについて
基本的に、遺産分割において葬儀費用を誰が負担するのかについては、当事者間での話し合いで解決できなければ、遺産分割を離れて、訴訟で解決することとなります。
なぜなら、葬儀費用を誰が負担するかという問題と、遺産をどう分けるのかという遺産分割の問題とは、本来別個のものと考えられているためです。
そもそも、相続は、プラスの財産だけでなく、「債務」も相続人が引き継ぎます。
ここでいう「債務」とは、原則、相続開始時点(亡くなった時点)で、亡くなった方(被相続人)が有していた債務のことを言います。
葬儀費用は、基本的に、被相続人が亡くなった後に発生する費用であるため、葬儀費用は、ここでいう「債務」には当たりません。
このような理由から、遺産分割と葬儀費用を誰が負担するかについては、別の問題となります。
もっとも、裁判所以外での話し合いの段階や、遺産分割調停の段階では、葬儀費用の費用分担も含めて話し合うことは可能です。
話し合いや調停で解決できない場合に初めて、訴訟で解決することになります。
なお、遺産分割審判では、葬儀費用の負担について、裁判所は判断しませんので、注意が必要です。
2 葬儀費用を誰が負担するか
一般的に、葬儀費用を誰が負担するのかについて、相続人全員での合意がある場合はそれに従うことになります。
また、被相続人の生前の指示がある場合、例えば、遺言書で「葬儀費用は遺産から出すように」との文言がある場合は、被相続人の遺志を尊重し、それに従うことになります。
それでは、葬儀費用の負担につき、相続人全員の合意がなく、かつ、被相続人の指示もない場合、葬儀費用は誰が負担することになるのでしょうか。
この点、葬儀費用の負担者に関しては明文の規定もなく、また、最高裁の判断もないため、個々の事案で具体的な事実関係を検討したうえで、誰が負担するのが適切かを個別に判断することとなります。
以下では、葬儀費用の負担に関し、代表的な見解を2つご紹介します。
⑴ 喪主負担説
喪主負担説とは、喪主が葬儀費用を負担すべきという説です。
この説の根拠は、葬儀を行うか否か、行うにしても、どの規模で行うかについて喪主が決定するため、葬儀費用も喪主が負担することが相当であるという考えによります。
この見解に立った裁判例としては、名古屋高等裁判所平成24年3月29日判決や平成26年3月28日判決などがあります。
近年の裁判例は、この説に立つものが相当数見られますが、この見解が通説ではありません。
参考リンク:名古屋高等裁判所平成24年3月29日判決/裁判所
⑵ 相続財産負担説
相続財産負担説とは、葬儀費用は遺産から支出すべきという説です。
この説の場合、すでに葬祭費用を負担した相続人は、各相続人に対して、その負担割合に応じて請求をすることができます。
この見解に立った裁判例としては、高松高裁昭和38年3月15日決定、東京地裁平成17年7月20日判決などがあります。
3 葬儀費用の負担を相続人の間で話し合っておくことが必要
このように、葬儀費用を誰が負担するのかについては、見解が分かれており、現状、統一的な答えがありません。
そのため、葬儀費用の負担で争いになりそうな場合は、相続人の間で話し合い、誰が負担するのかを決めてから、葬儀費用を支払われた方が良いでしょう。
これから遺言書を作成するという方は、遺言書の中に、葬儀費用を遺産から支出することについて記載しておいた方が、後々、相続人間で葬儀費用の負担を巡って、揉めることを回避することができます。
葬儀費用でお困りの場合は、一人で悩まれず、専門家にご相談されることをおすすめします。
私たちは、相続について原則無料で承っており、相続に精通した弁護士や税理士などの専門家が対応させていただきます。
また、事務所でのご相談だけでなく、電話やテレビ通話による相談も承っておりますので、相続でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。