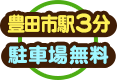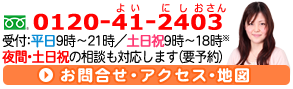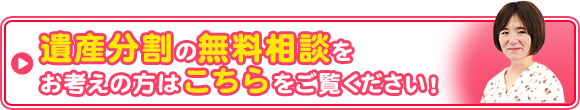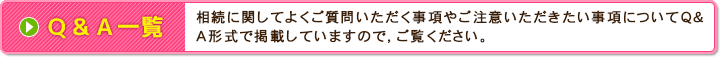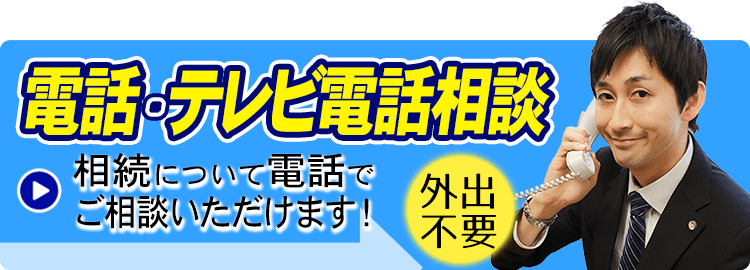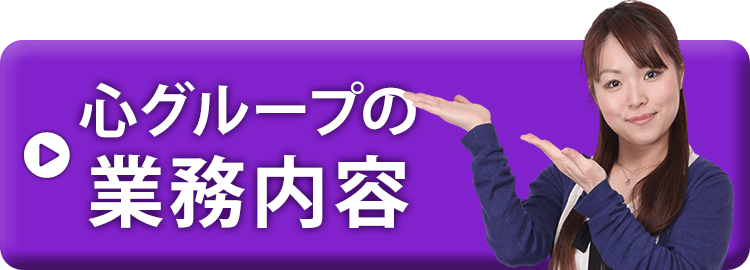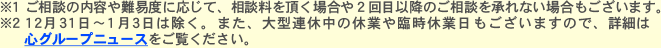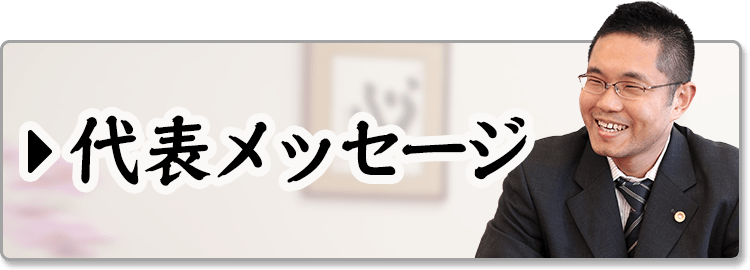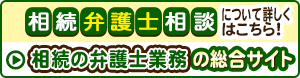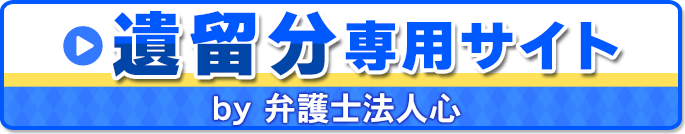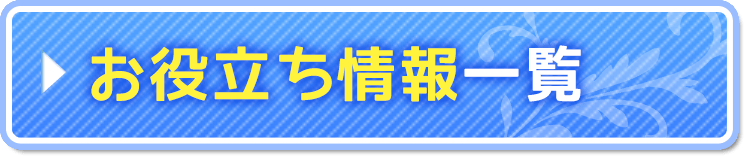相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割
1 原則として成年後見人の選任が必要
相続人の中に認知症の方がいる場合、認知症の程度が重篤の場合では、原則、認知症の相続人に成年後見人を就けなければ、遺産分割をすることができません。
成年後見人を就けずに遺産分割をしてしまうと、後日、遺産分割協議自体が無効として争われてしまう可能性があります。
また、万が一、遺産分割協議が無効になると、相続人の中に認知症の人がいることを知ったうえで遺産分割協議に参加した人は、遺産分割協議の無効によって損害を被った人から、損害賠償請求をされる危険性もあります。
たとえば、父が亡くなり、相続人は重度の認知症の長男と判断能力に問題がない二男の二人のみであり、二男は、長男に成年後見人を就けず、遺産分割協議を行い、遺産全てを自分のものにした場合、長男が亡くなった後、長男の相続人は、二男に対し、遺産分割協議の無効を主張することができます。
また、すでに二男が遺産を使っている場合は、長男の相続人は、二男に対して損害賠償請求を行うことができます。
さらに、長男の相続人は、二男が父の遺産であった土地を他人に売却した場合でも、その他人に対し、長男の相続分(2分の1)の土地を返還するよう請求するかもしれません。
その結果、二男から土地を買った他人としては、土地について不完全な権利しか取得できなくなるため、二男に対して、損害賠償請求を行う可能性があります。
このように、相続人に認知症の人がいる場合、その人の認知症の程度次第では、成年後見人を立てる必要があり、万が一、成年後見人を立てずに遺産分割を行ってしまうと、後々、遺産分割協議が無効になったり、損害賠償請求をされたりと、大変なことになる可能性があります。
2 成年後見人を選任しなくても良い場合
他方、相続人に認知症の人がいる場合でも、認知症の程度が極めて軽度であり、遺産分割を行うだけの判断能力を有している場合は、成年後見人を就けずに、遺産分割協議を行うことができます。
もっとも、遺産分割を行うだけの判断能力の程度については、遺産分割協議の内容(誰がどの財産を取得するかなど)や認知症の程度等によっても異なり、明確な基準があるわけでもないため、安易に「認知症が軽度だから成年後見人立てなくても大丈夫」と考えるのは危険です。
また、不動産に関しては、判断能力がない相続人がいたとしても、法定相続分で相続登記を行うことはできます。
たとえば、相続人に長男(判断能力なし)と二男(判断能力あり)がいる場合、遺産である不動産について、二男の単独登記申請で、2分の1ずつの権利を相続したものとして、相続登記を行うことはできます。
なお、預貯金については、金融機関ごとに取扱が異なるため、法定相続分どおりに分けたとしても、手続ができない可能性もありますので、注意が必要です。
3 認知症になる前に遺言の作成が必須
このように、相続人に認知症の人がいる場合、原則として成年後見人を選任する必要があります。
また、一度、成年後見人が選任されてしまうと、現行法では、その相続人が判断能力を取り戻すまでか、その相続人が亡くなるまで、成年後見人が就き続けることになります。
そのため、成年後見人に専門家が就いた場合、基本的に、その相続人が亡くなるまで一生に渡って成年後見人の費用(月3万円~5万円前後)がかかり続けることになり、その相続人やその家族に対して、成年後見人を立てることで負担がかかる可能性があります。
このように、相続人に認知症の人がいる場合、他の相続人だけでなく、その認知症の相続人自身やその家族に対しても、負担がかかる可能性があります。
これを回避しようと思えば、基本的に、遺言を作成することが適切です。
遺言があり、遺言執行者を選任しておれば、相続人に認知症の人がいたとしても、基本的に遺言の内容を実現することができます。
なお、遺言の書き方次第では、相続人に認知症の人がいると、遺言の内容が実現されない可能性もありますので、遺言の作成については、専門家にご相談されることをおすすめします。