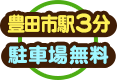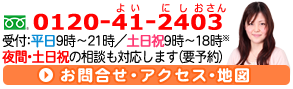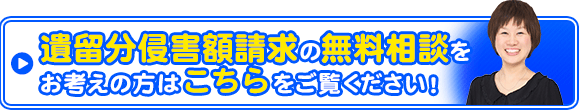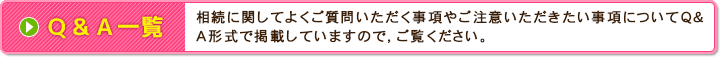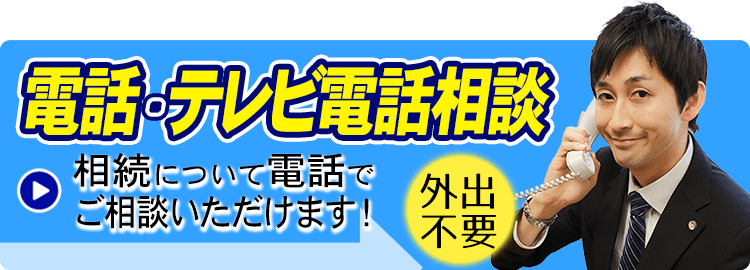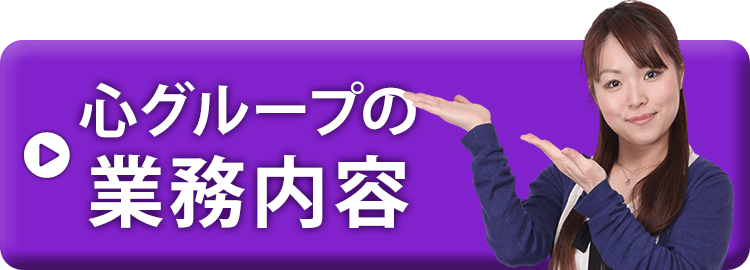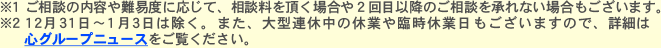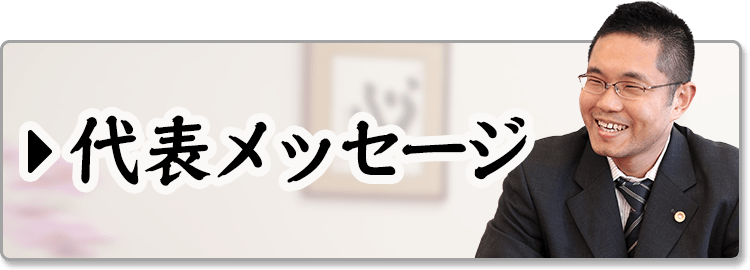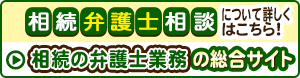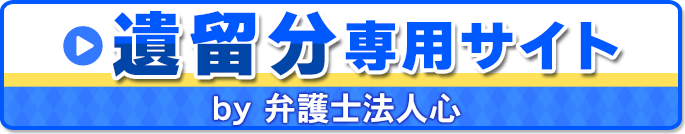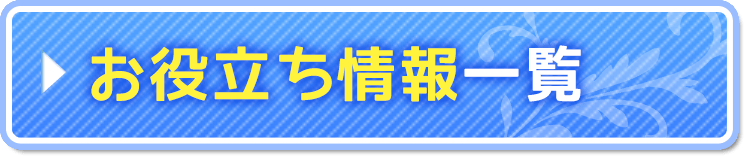遺留分侵害額請求の流れと依頼する専門家の選び方
1 期限内に請求しないと遺留分侵害額請求ができなくなる
遺留分侵害額請求は1年間の期限があり、これを過ぎてしまうと遺留分侵害額請求をしても認められなくなってしまう場合があります。
そのため、遺留分侵害額請求を行う場合は、できるだけ早めに手続きを行う必要があります。
以降では、遺留分侵害額請求の流れについて説明します。
2 遺留分侵害額請求の流れ
⑴ 概要
遺留分侵害額請求を行う場合の流れとしては、以下の通りです。
①遺言書で遺産を多くもらった相続人や生前贈与された相続人等(以下、「遺留分侵害者」といいます)に対し、内容証明郵便にて、遺留分侵害額請求を行う旨を伝えます。
②遺留分侵害者や他の相続人と協議し、遺留分侵害額請求額を決めます。
協議で合意できれば、合意書を作り、遺留分侵害額が支払われれば手続きは終了となります。
③遺留分侵害者との協議が整わない場合、遺留分侵害者の住所地を管轄する家庭裁判所にて、遺留分侵害額の調停手続きを行います。
調停でまとまれば、調停調書が作られます。
そして、遺留分侵害額が支払われれば、手続きは終了となります。
④調停でもまとまらない場合は、地方裁判所にて、遺留分侵害額請求の訴訟を行うことになります。
訴訟で和解ができれば、和解調書が作られます。
和解もできない場合は、判決によって、遺留分侵害額が決まります。
なお、判決が不服の場合は、高裁に控訴でき、控訴審の判決にも不服の場合は、最高裁判所に上告することができます。
⑵ 手続きの詳細
① 遺留分侵害額請求を行う旨の通知
遺留分侵害額請求は、被相続人が亡くなったことと、遺留分を侵害する遺言書の内容や贈与などがあったことを知った時から、1年以内に、遺留分侵害者に対して、遺留分侵害額請求を行う旨を伝える必要があります。
たとえば、被相続人が令和4年12月1日に亡くなり、遺言書の存在を令和5年11月10日に知った場合は、令和6年11月10日が期限となります。
また、遺留分侵害額請求を行う旨の通知を伝える際も、口頭や普通郵便だと証拠として残らないため、一般的には、内容証明郵便という送った内容が記録に残る書類で、遺留分侵害額請求を行う旨の通知を行うことが多いです。
実際、口頭だけで遺留分侵害額請求を行う旨を伝えたが、遺留分侵害者が「そんな話は聞いていない」としらを切り、トラブルになった事例もあります。
そのため、遺留分侵害額請求を行う場合は、必ず、内容証明郵便にて請求する旨を伝えた方が良いでしょう。
参考リンク:郵便局・内容証明
② 遺留分侵害者との協議
遺留分侵害者との協議がまとまった場合は、合意書を作ることになります。
この合意書の内容としては、被相続人の名前や逝去した日、遺留分侵害額の金額や支払い期限、支払い方法などを記載することになります。
③ 遺留分侵害額の調停
協議がまとまらない場合、遺留分侵害者の住所地を管轄する裁判所に、調停を申し立てることになります。
遺留分侵害者の住所地が豊田市の場合は、名古屋家庭裁判所岡崎支部に申し立てを行います。
申立ての際は、被相続人や相続人の戸籍謄本、住民票や戸籍の附票、遺言書や贈与契約書、遺産の内容が分かる書類(残高証明書や登記事項全部証明書等)が必要になります。
なお、申立の詳細については、裁判所のホームページをご確認ください。
参考リンク:裁判所・遺留分侵害額の請求調停
④ 遺留分侵害額の訴訟
調停でもまとまらない場合は、地方裁判所に遺留分侵害額請求の訴訟を提起することになります。
なお、そもそも調停でもまとまりそうにない場合は、調停を経ずに訴訟を提起することもできます。
訴訟を提起する裁判所は、被相続人の住所地を管轄する地方裁判所や遺留分侵害者の住所地を管轄する裁判所、遺留分請求者の住所地を管轄する裁判所等に提起することができます。
たとえば、遺留分請求者が豊田市にお住まいの場合は、名古屋地方裁判所岡崎支部に訴訟を提起することができます。
訴訟を提起する際は、調停の場合と同様の書類が基本的に必要になります。
なお、訴訟までに発展するケースだと、解決までに2年~3年程度かかることがあります。
3 依頼する専門家によって遺留分侵害額請求額が変わる場合もある
⑴ 依頼する専門家によって遺留分侵害額が変わる理由
遺留分侵害額の請求額は、依頼する専門家によっても金額が変わる場合があります。
なぜ依頼する専門家によって遺留分侵害額が異なるかというと、専門家の中には遺留分に詳しくない方もおり、遺産の評価方法や法律の解釈次第では、遺留分の金額が大きく変わることがあるためです。
たとえば、遺産に建物が建っている土地がある場合、土地を評価するにしても、固定資産税評価か路線価、相続税評価や公示価格からの評価、実勢価格での評価などの評価方法があり、どの評価方法によって遺留分を計算するかによって、遺留分の金額が変わります。
また、建物が老朽化している場合、解体費を控除して更地として評価するのか、それとも老朽化した建物が建った土地として評価するかによっても、土地の金額が異なります。
法律の解釈においては、被相続人から相続人に生前贈与がある場合、被相続人が持ち戻し免除を行うことがあります。
持ち戻し免除とは、簡単にいうと、遺産分割の際に、生前贈与を考慮せずに、遺産の分け方を決めるように相続人に指示することを言います。
この持ち戻し免除については、遺産分割において考慮する必要がありますが、遺留分侵害額請求では、基本的に考慮する必要はありません。
もっとも、専門家の中には、持ち戻し免除を遺留分侵害額請求でも適用されると勘違いされている方もおり、勘違いしたままだと、遺留分侵害額請求額も間違えている可能性があります。
⑵ 遺留分に強い専門家に依頼する
このように、遺留分侵害額については、土地の評価や法解釈によっても金額が異なりますが、専門家の中には、このような土地の評価が大きく異なることや持ち戻し免除などの法律解釈について知らない方もおり、そういった方に依頼してしまうと、遺留分侵害額が少なくなる可能性があります。
そのため、遺留分侵害額の請求をお考えの方は、遺留分に強い専門家にご依頼されることをおすすめします。
遺留分侵害額請求権の時効 未登記の建物を相続したらどうすればいいか