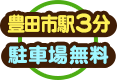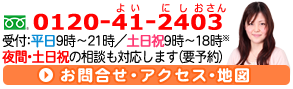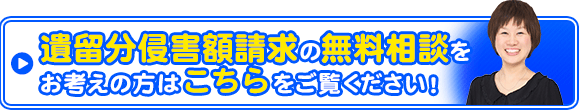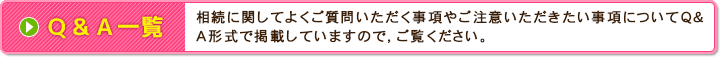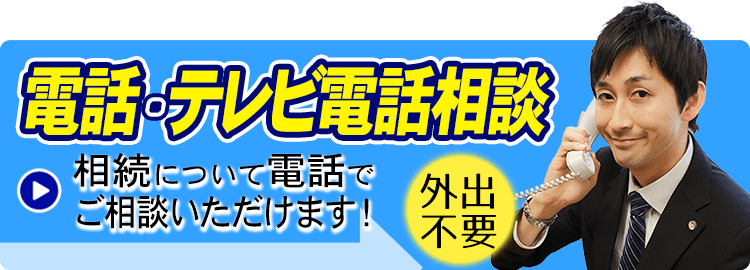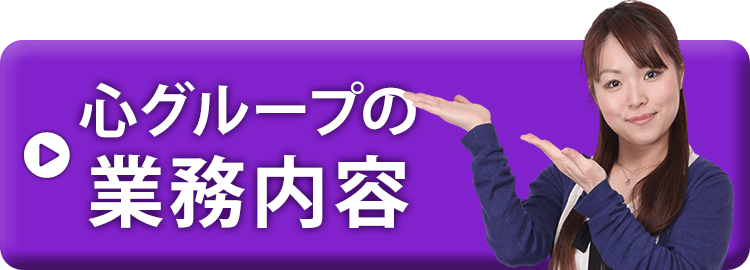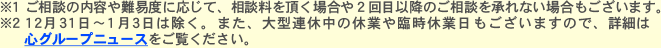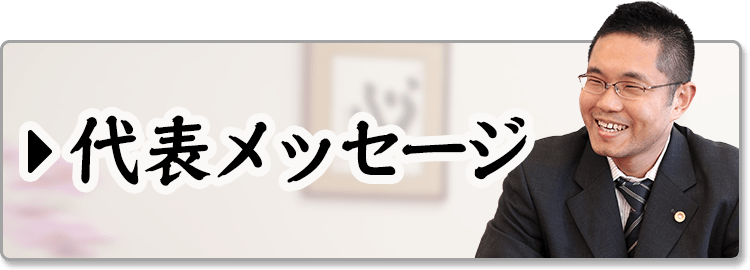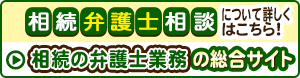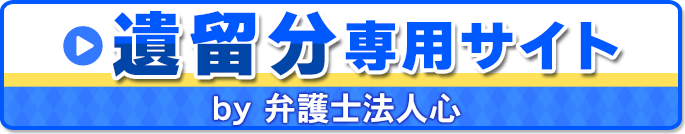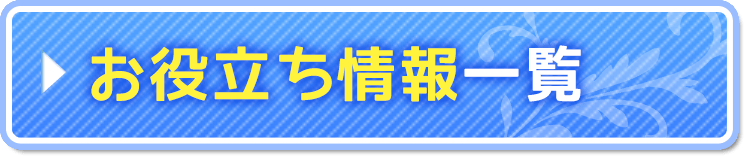遺留分侵害額請求権の時効
1 基本は一年以内に請求する必要がある
遺留分侵害額請求権には期限があります。
たとえ1日だけであっても、期限を過ぎてしまうと時効が完成し、遺留分を請求しても認められなくなる可能性がありますので注意が必要です。
この遺留分侵害額請求権の時効は、相続の開始(被相続人が亡くなったこと)と、遺留分を侵害する遺言書の存在や生前贈与などがあったことを知った時から1年です。
また、遺言書の存在や生前贈与の存在を知らなかったとしても、相続が開始してから10年が経過すると時効が完成してしまいます。
2 時効の具体例
例えば、父が被相続人、相続人が長男と長女の場合で、父が長女に豊田にある自宅を含む全財産を渡す遺言書を作成していたケースについて考えてみます。
父が令和5年12月1日に亡くなり、長男は同日に父が亡くなったことを知り、その後、令和6年1月1日に「全財産を長女に渡す」旨の、つまり長男の遺留分を侵害する内容の遺言書の存在を知ったとします。
この場合、長男は、令和5月12月1日に相続の開始を知り、令和6年1月1日に遺留分を侵害する遺言書の存在を知ったため、令和6年1月1日の時点から1年以内に、長男は長女に対し、遺留分侵害額請求をする必要があります。
また仮に、長男が、父が亡くなったことや、遺言書の存在を知らなかったとしても、父が亡くなった時から10年が過ぎてしまうと、遺留分侵害額請求が認められない可能性があります。
3 遺留分侵害額請求をした後の時効
遺留分侵害額請求をした後でも、5年以内に訴訟等を行わないと、時効により、請求が認められなくなる可能性があります。
先ほどの例に当てはめると、長男が長女に令和6年1月1日に遺留分侵害額請求をした場合、そこから5年以内に長男が訴訟等をしないと、時効により、遺留分が請求できなくなるおそれがあります。
そのため、遺留分侵害額請求をした後であっても、訴訟等をせずに放置してしまうと、請求が認められない場合があります。
4 遺言書の無効を主張している場合の落とし穴
専門家でも間違える落とし穴として、遺言書が存在し、その無効を主張し、遺産分割協議をするように主張している場合であっても、必ず、遺留分侵害額請求は期限内に行う必要があります。
万が一、遺言書の無効と遺産分割協議を行いたいとの主張だけをしている場合に、遺言書が有効と判断されると、遺留分が時効で認められなくなる可能性があります。
実際、専門家でも、この点を理解していない方もいますので、十分注意する必要があります。
なお、遺言書の無効を主張している場合だと、遺留分請求をする際に、「まず、遺言書自体が無効である。次に、万が一、遺言書が有効な場合、遺留分請求をする」という形で請求すれば、時効の問題はクリアできます。
5 遺留分侵害額請求の方法
遺留分侵害額請求の方法については口頭でも構わないものとされています。
しかし証拠に残る形で請求しておかないと、請求自体がなかったとされてしまう事態になりかねません。
具体的には、内容証明郵便にて、相続人の住所宛に、遺留分侵害額請求の通知を送る方法をおすすめします。
内容証明郵便であれば、いつ遺留分の請求をしたのかの証拠とすることができます。
口頭で伝えるだけですと、後から「言った、言わない」の問題となってしまうおそれがあります。
そこで万が一請求していないと認められてしまうと、遺留分を取得することができなくなってしまいます。
6 遺留分の請求は弁護士にご相談ください
このように、遺留分侵害額請求については、時効との関係で、一歩間違えると、請求自体が認められなくなります。
遺留分侵害額請求をお考えの方は、一度、相続に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。
なお、当法人では、遺留分について原則無料でご相談を承っており、相続を集中して扱う弁護士がご相談を承ります。
具体的な相談のお申込みについては、フリーダイヤル、もしくはメールフォームから、当法人までお問い合わせください。
繰り返しになりますが、遺留分侵害額請求は、たとえ1日だけでも期限を過ぎてしまった場合、認められなくなる可能性がありますので、なるべくお早めにご相談ください。
相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割 遺留分侵害額請求の流れと依頼する専門家の選び方