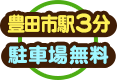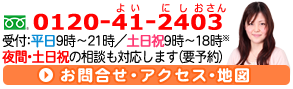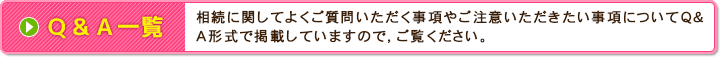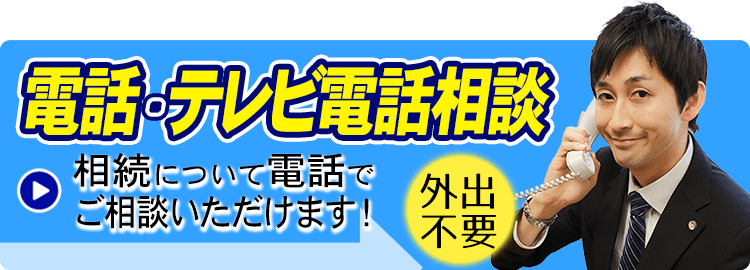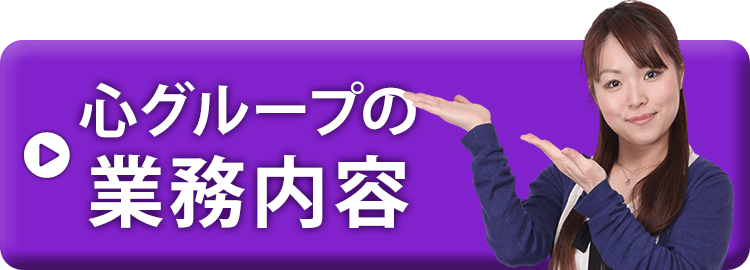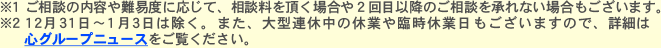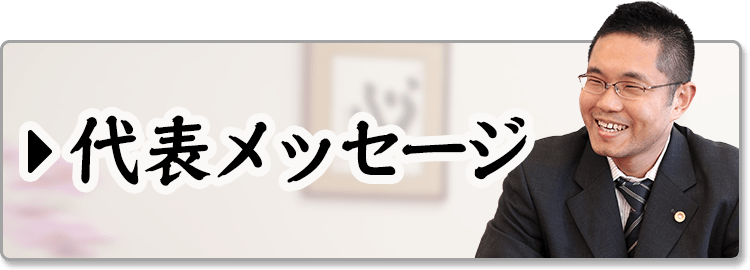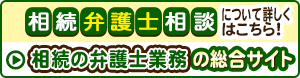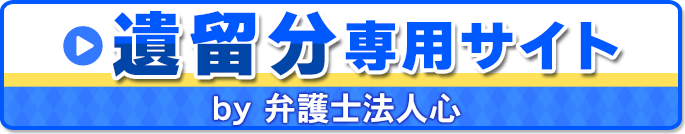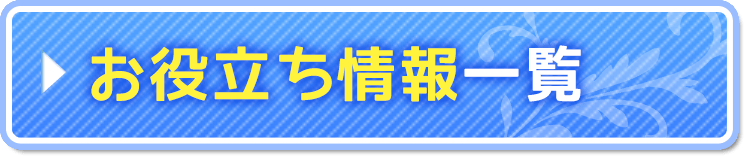死後離縁手続きについて
1 死後離縁とは
死後離縁とは、養親または養子が亡くなった場合に、亡くなった方との養子縁組を終了させる手続きです。
実際に利用されるケースとしては、養親の実子に対して扶養義務を負いたくない場合や、感情的に養子縁組を解消したいという場合に利用されます。
2 死後離縁と相続の関係
死後離縁を行っても、離縁する前の法律関係には影響がありません。
したがって、養親の遺産は、死後離縁を行った場合でも相続することになります。
そのため、養親の遺産が、預貯金や不動産、株式等のプラスの財産よりも、借金・ローンなどのマイナスの財産が多かったような場合でも、すでに発生している相続には影響しません。
死後離縁では養親の借金から免れることはできませんので、借金を相続したくない場合には、相続放棄などの別の方法も検討する必要があります。
3 死後離縁手続きの流れ
死後離縁をするには、裁判所に対して許可の審判をもらい、審判が出たことを役所に届け出ることによって完了します。
そのため、養親の親族等に、「縁を切る」と伝えても、法的には離縁が認められませんので注意が必要です。
また、必ずしも裁判所の許可が出るとも限りませんので、ご注意ください。
具体的な死後離縁の流れとしては、①必要書類を裁判所に提出する、②裁判所からの照会書等への対応、③死後離縁許可書及び審判確定書の取得、④必要書類を市役所へ提出、という流れになります。
4 ①必要書類を裁判所に提出する
⑴ 必要書類の取得
死後離縁許可申立を行う際に必要になる書類は、申立書、800円分の収入印紙、切手、養親と養子の戸籍謄本が必要になります。
申立書については、裁判所のホームページに書式がありますので、それをもとに必要事項を記載します。
参考リンク:裁判所・死後離縁許可の申立書
切手については、裁判所ごとに必要な額が異なりますので、事前に裁判所に問い合わせた方が良いでしょう。
養親と養子の戸籍謄本については、亡くなった方の亡くなったことが分かる戸籍謄本が必要です。
また、戸籍謄本については、期限はありませんが、できる限り最新のものを取得しましょう。
⑵ 裁判所に申請書等の必要書類を提出する
提出する裁判所は、申し立てる人の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
直接裁判所に持参せずとも、郵送で行うことも可能です。
5 ②裁判所からの照会書等への対応
裁判所に必要書類を提出した後、裁判所から照会書が届く場合や裁判官と面談を行う場合等があります。
照会書が届く場合は、必要事項を記載して、裁判所に提出します。
裁判官と面談する場合は、直接裁判所に行って、裁判官からの質問に答えます。
照会書の回答内容や裁判官からの質問への回答次第では、死後離縁が認められなくなる場合があります。
たとえば、養親の相続で多大の利益を受けながら、不当に扶養義務を免れる場合など、「死後離縁の申立てが法定血族間の道義に反する恣意的で違法なもの」であるときは、死後離縁が認められない場合があります。
6 ③死後離縁許可書及び審判確定書の取得
書面照会や裁判官からの面談等が終わると、1~2週間前後で通知が送られてくるか、面談日当日に結果が言い渡されます。
内容としては、死後離縁を認めますという許可審判か、死後離縁を認めませんという却下審判が出ます。
死後離縁が認められた場合、許可審判書と確定証明書の申請書が送られてきますので、この確定証明書の申請書を裁判所に提出します。
その際、150円の収入印紙と、郵送の場合は、返信用の切手が必要になります。
その後、確定証明書が裁判所から送られてきますので、確定証明書を受け取ります。
7 ④必要書類を市役所へ提出
裁判所から死後離縁が認められた場合、養子離縁届を養親か養子の本籍地または所在地の市区町村役所へ提出します。
その際、裁判所から取得した審判許可書と確定証明書と届出をする人の本人確認書類、印鑑が必要です。
本籍地以外の役所に提出する場合は、養親及び養子の戸籍謄本が必要になります。
その後、養子離縁届等に不備がなければ、死後離縁が認められます。
なお、離縁により養子が縁組前の氏に戻る場合に、7年以上の縁組期間があれば、離縁後3ヵ月以内に、離縁の際に称していた氏を称する届をすることで、縁組中の氏をそのまま使用することもできます。
この届は、離縁届と同時に行うこともできます。
8 死後離縁をご検討の際は専門家に相談を
このように死後離縁を行う場合は、裁判所での手続き等を経る必要があり、養親と養子の関係次第では、養子縁組が認められないこともあります。
また、死後離縁を行い、裁判所で認められた後に、死後離縁を撤回することは認められていません。
そのため、死後離縁を行う場合には、本当に行っても構わないのか、死後離縁を行った後の法律関係はどのようになってしまうのか、専門家へしっかりと相談してから手続きをとられることをおすすめします。
当法人では、死後離縁を含む相続について、無料相談も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。