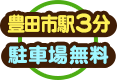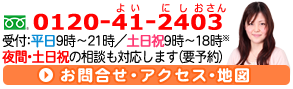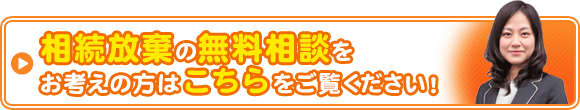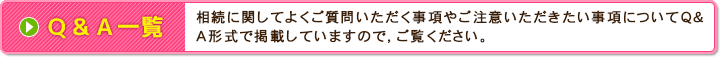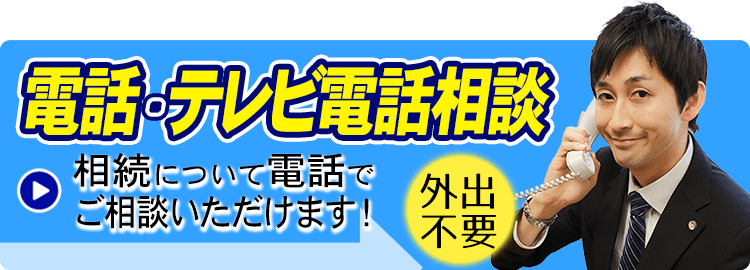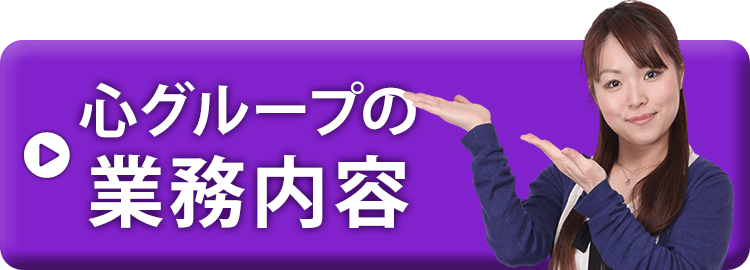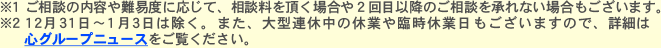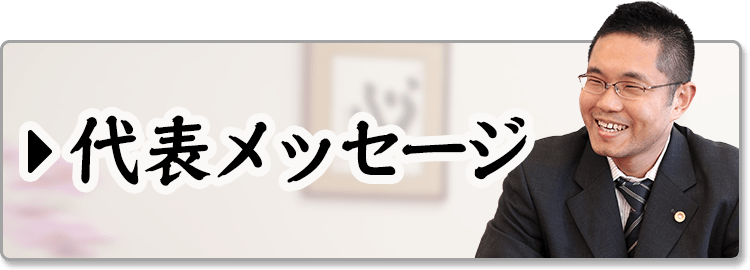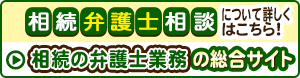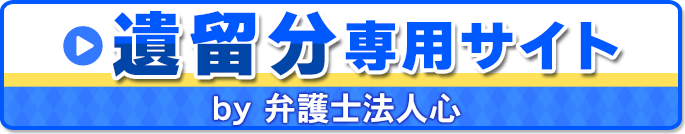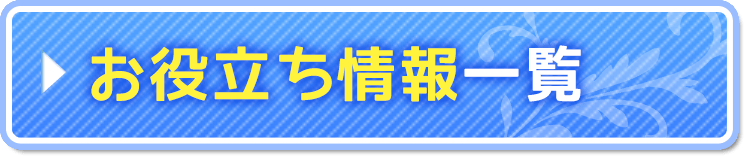相続放棄申述受理証明書の取得方法
1 相続放棄申述受理証明書について
相続放棄申述受理証明書とは、簡単にいうと、相続放棄が認められたことを証明する書類のことです。
相続放棄が裁判所で認められた場合、相続放棄を申立てた人には、「相続放棄申述受理通知書」という書類が送られてきます。
しかし、この通知書は「相続放棄が認められました」ということを申立人に通知するものであって、相続放棄が認められたことを直接証明してくれるものではありません。
そこで、「相続放棄が認められました」ということを証明するための書類として、家庭裁判所が発行する相続放棄申述受理証明書を取得する必要がある場合があります。
参考リンク:裁判所・家事事件に関するその他の手続
2 相続放棄申述受理証明書が必要になるケース
基本的に、相続放棄申述受理証明書が必要になる場合として、以下のケースが挙げられます。
①相続放棄をした人以外が、預貯金の解約や不動産の名義変更等の手続きを行う場合
②相続放棄申述受理通知を紛失してしまった場合
なお、亡くなった方の債権者に対する通知については、基本的に相続放棄申述受理通知書の写しで対応することが可能です。
⑴ ①相続放棄をした人以外が預貯金の解約等の手続きを行う場合
例えば、相続人が2人おり、そのうちの1人が相続放棄をした場合、相続放棄をしていない人が、亡くなった方の預貯金の解約や不動産の名義変更を行う際に、相続放棄申述受理通知書の原本か、相続放棄申述受理証明書の原本が必要になります。
ここで、相続放棄をした人が協力的であれば、相続放棄申述受理通知書を貸してもらって手続きが行えます。
しかし、相続放棄をした人があまり協力的でなかったり、疎遠であったりした場合は、手続きを進めるためには、相続放棄申述受理証明書を取得する必要があります。
なお、金融機関によっては、相続放棄申述受理通知書ではなく、相続放棄申述受理証明書が必要になる場合もあります。
⑵ ②相続放棄申述受理通知書を紛失してしまった場合
相続放棄申述受理通知書を紛失してしまうと、再発行ができませんので、相続放棄申述受理証明書を発行する必要があります。
3 相続放棄申述受理証明書の取得方法
実際に、相続放棄申述受理証明書を取得するための手続きについて、ご紹介します。
もっとも、家庭裁判所ごとに、申請書の書式や必要書類が異なる場合もありますので、手続きの際は家庭裁判所にご確認ください。
⑴ 相続放棄を行った方が取得する場合
相続放棄をした方が相続放棄申述受理証明書を取得する場合、相続放棄申述受理証明書の交付申請書に必要事項を記入し、150円分の収入印紙等を、相続放棄を行った家庭裁判所へ郵送、または、窓口に持参します。
交付申請書については、相続放棄申述受理通知書とともに送られてくる場合もあります。
交付申請書は、裁判所のホームページでダウンロードすることも可能です。
⑵ 相続放棄を行った方以外
相続放棄を行った方以外が相続放棄申述受理証明書を取得される場合、以下の書類が必要になります。
① 申請書
申請書については、必要事項をご記入いただき、押印ください。
なお、押印は、認印で問題ありません。
② 相続放棄をした方との利害関係が分かる書類
相続放棄申述受理証明書の取得を希望される方が相続人の場合は、亡くなった方の戸籍謄本や相続放棄を行った方の戸籍謄本、相続関係図等が必要になります。
必要になる書類は、ケースによって大きく異なってきますので、申請をする際に裁判所にお問い合わせください。
③ 法人が申請人となる場合には、商業登記簿の謄本または資格証明書
3か月以内に発行されたもの
④ 弁護士や申請人となる会社の社員に申請を代理してもらう時には、委任状
⑤ 1通150円分の収入印紙
3通必要になる場合は、450円分の収入印紙が必要です。
⑥ 郵送で行う場合、身分証のコピー、返信用封筒
⑦ 窓口で行う場合は、身分証、印鑑