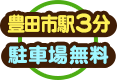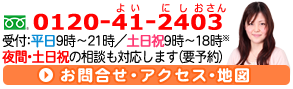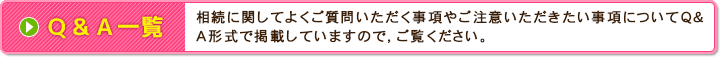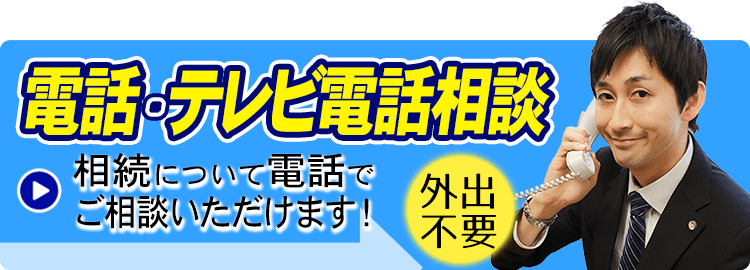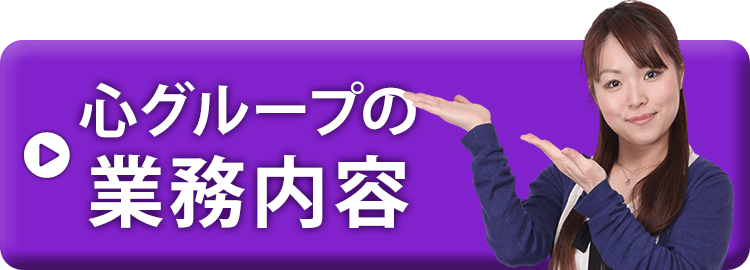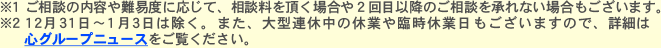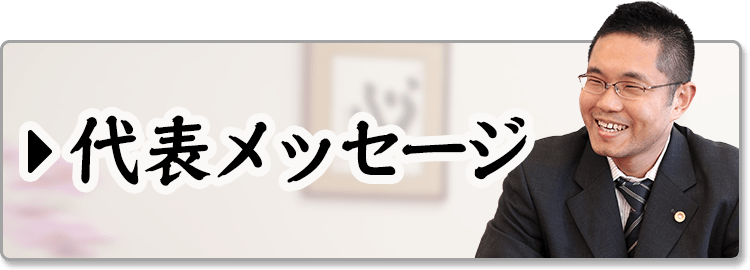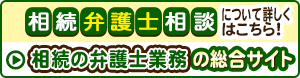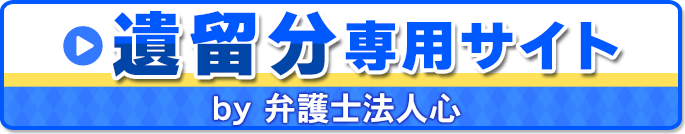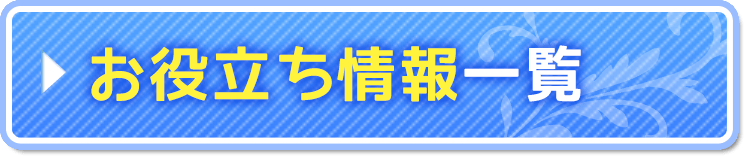相続税対策としてできること
1 生前贈与の活用
「相続税対策といえば生前贈与」と言われるように、相続税対策の代表的なものとして、生前贈与を活用する方法が挙げられます。
具体的には、子や孫らに、年間110万円を贈与するという暦年贈与の方法や、教育資金贈与の特例、住宅資金贈与の特例を活用する方法などです。
これらの方法については、比較的取り組みやすく、効果もそれなりにあるため、多くの方が利用されている印象があります。
もっとも、これらの方法については、今後の税制改正の結果次第では、そもそも使えなくなったり、使ったとしても効果がほとんどなくなったりする可能性があります。
実際、毎年110万円を贈与するという暦年贈与については、今後の改正内容次第では、そもそも相続人に暦年贈与しても、相続税対策にならない可能性もあります。
また、教育資金贈与の特例や住宅資金贈与の特例についても、適用できる条件が厳しくなっており、今後は、一部の人しか使えなくなる可能性があります。
このように、生前贈与を活用して相続税の対策をするには、今後の税制改正にも着目して、対策をしていく必要があります。
2 生命保険の活用
生命保険を活用した相続税対策は、保険の内容さえ見極めれば、大きな相続税対策の効果があります。
そもそも、死亡保険金について、法定相続人の数×500万円までは、相続税の課税対象にはなりません。
例えば、相続人が3人の場合、受取人が相続人の死亡保険金については、1500万円まで相続税がかからなくなります。
また、実際に死亡保険金を活用した対策例として、相続人が3人おり、遺産が預貯金1億円のケースでも考えてみましょう。
特に対策を取らなかった場合、相続税の総額は630万円となります。
しかし、預貯金1億円のうち、1500万円を生命保険に代え、相続人を受取人とした場合、1500万円の死亡保険金は相続税の対象から外れるため、相続税の総額は、405万円となります。
預貯金を死亡保険金に代えるだけで、先ほどのケースだと200万円以上の相続税対策となります。
このように、生命保険を活用した相続税対策は非常に有効であり、対策の方法としても比較的簡単です。
もっとも、注意点として、保険の内容次第では、相続税対策にならないケースや、反対に預貯金として持っておいた方が良いケースもあります。
保険会社の担当者の中には、相続税についてあまり詳しくない方や間違った知識をお持ちの方もいるため、生命保険については、慎重に検討されることをおすすめします。
3 不動産の活用
不動産を活用した相続税対策は、効果が大きい反面、実際に行うことが難しいものがあります。
不動産を活用した相続税対策としては、代表的なものに、預貯金を使う、または借入をして、賃貸不動産を購入する方法が挙げられます。
そもそも、相続税の計算上、相続財産については、預貯金で持っておくよりも不動産にした方が、相続税が安くなる場合があります。
例えば、預貯金で1億円を持つよりも、それで1億円の土地を買った方が、小規模宅地等の特例等が適用されることにより、相続税が大幅に安くなることがあります。
また、不動産を購入する際に借入をした場合、借金の額だけ遺産の総額が小さくなりますので、結果的に相続税も安くなります。
もっとも、この対策で気をつける点としては、借入をして、賃貸不動産を購入したはいいが、家賃収入がほとんど入らない場合には、結果的に多額の借金だけが残る結果になる可能性があるということです。
不動産会社の中には、相続税対策になるという謳い文句で、賃貸不動産の購入をすすめてくる方もいます。
しかし、不動産業者の中には相続税についてあまり詳しくなく、誤った知識を持っている方もいます。
誤った認識のもとで対策をしても、結果的に、多額の借金だけしか残らないといったケースもありますので注意が必要です。
そのため、不動産を活用して相続税対策を行う場合は、相続税に詳しい税理士のアドバイスのもと、信頼できる不動産会社と協力して行うことが必須です。
4 相続税対策は相続税に詳しい税理士に必ずご相談ください
上記のように、相続税対策として、生前贈与や生命保険、不動産を活用する方法があります。
これらの方法については、適切に行えば相続税対策になる反面、よく分からないまま行ってしまうと、相続税対策にならなかったり、反対に、多額の借金を背負うことになったりする場合があります。
専門家の中には、相続税について間違った知識を持っている方がいます。
また、税理士の中にさえ、間違った知識を持っており、間違ったアドバイスをする方もいます。
間違ったアドバイスを鵜呑みにしてしまうと、相続税対策にならないどころか、大きなデメリットを被るおそれもありますので、相続税に詳しい税理士に相談することが大切です。
相続税対策について相談する場合は、相続税対策に詳しい税理士にご相談のうえ、対策を進めていくことをおすすめします。
未登記の建物を相続したらどうすればいいか 相続で弁護士をお探しの方へ