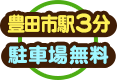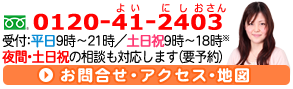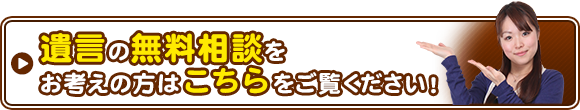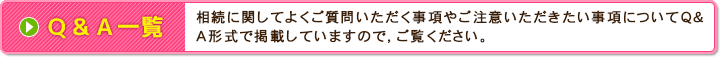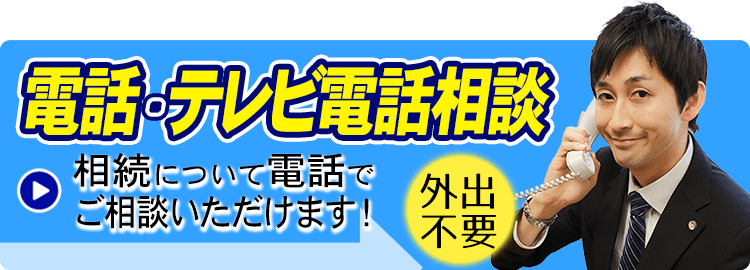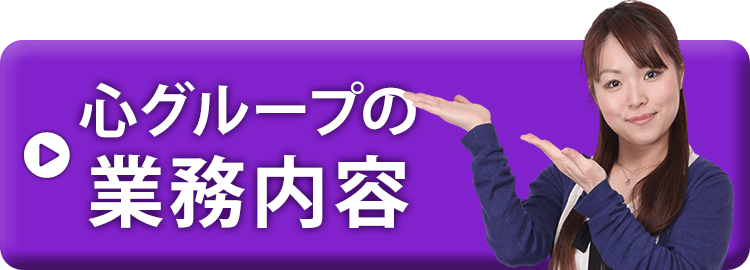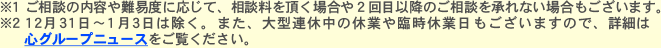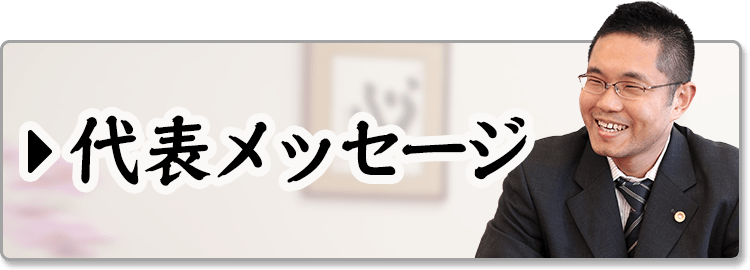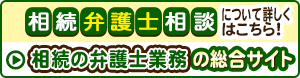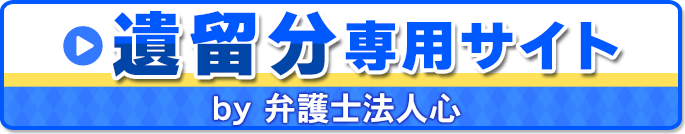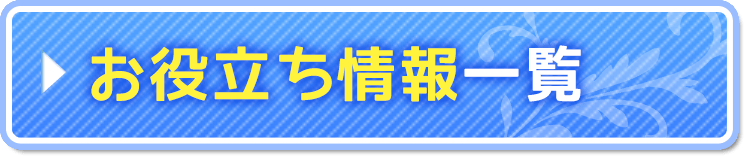遺言作成の流れ
1 遺言の内容を決める
遺言書作成にあたって、まずは遺言の内容を決めることになりますが、内容を決めるうえでの注意点があります。
以下で、その注意点をご説明いたします。
⑴ 抽象的な内容を書かない
遺言の内容が抽象的だと、最悪、遺言書の効力が認められない可能性があります。
例えば、「長男にすべての財産を託す」や、「財産を長女に任せる」といった内容の遺言は、内容が「全財産を相続させる」なのか、それとも「遺産の管理を任せる」だけなのか明確ではありません。
そのため、相続人の間でもめる原因にもなりますし、「遺産を相続させる」意味であるのに、その効力が認められない可能性もあります。
実際、こういった抽象的な文言であったために、争いになった事例も多々存在します。
そうならないようにするためにも、遺言書の内容は明確にすることが大切です。
遺産を渡したい場合は、「長男にすべての財産を相続させる」というように書くことをおすすめします。
⑵ 遺産を書きもらさない
遺言書にすべての財産を書いておかないと、後々、相続人同士でもめる原因になり得ます。
例えば、「自宅は長男に渡すが、預貯金は兄弟で話し合って決めてください」といった内容だと、預貯金をどう分けるかで、相続人同士がもめてしまうかもしれません。
また、よくある落とし穴として、現金や預貯金等のすべての金融財産を渡したい場合に「現金を長男に相続させる」と記載してしまうケースがあります。
この書き方だと、現金のみが長男に相続されると解釈され、預貯金などの遺産については、遺言書では何も書かれていないとみなされる場合があります。
⑶ 遺留分に注意する
遺言書の内容が、特定の相続人のみに有利な内容になっていると、他の相続人の遺留分を侵害することになり、トラブルを起こすきっかけになります。
遺留分とは、簡単にいうと、相続人に保証された最低限の相続の権利のことをいい、遺言書で全く渡さないと書いたとしても、遺留分自体は消えません。
例えば、相続人が長男と長女の2人の家庭で、遺言書の内容が「長女に全財産を渡す、長男には何も渡さない」といった内容だったとしても、長男は長女に対して、遺留分の請求をすることができます。
具体的には、長男は、長女に対して、遺産の4分の1の額のお金を請求することができてしまいます。
このように、遺言書の内容が、特定の相続人に有利なものであるケースですと、他の相続人が特定の相続人に対して遺留分の請求ができる場合があり、後々、相続でもめる原因にもなります。
遺留分での揉め事を避けるためには、なるべく法定相続分通りの遺言書の内容にするか、もしくは、遺留分対策を行う必要があります。
遺留分対策については、専門的かつ複雑な知識が必要ですので、対策を検討する際は、一度、専門家にご相談されることをおすすめします。
2 遺言の種類を決める
遺言書の内容が決まった後は、遺言の種類を決めます。
遺言書には、よく使われるものとして、①手書きで作成する自筆証書遺言と②公証役場で作成する公正証書遺言があります。
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選んだ方が良いかについては、基本的に、公正証書遺言の方をおすすめしています。
理由としては、公正証書遺言の方が、公証人による遺言の内容のチェックが入るため、遺言書作成に失敗するリスクが少ないからです。
自筆証書遺言だと、遺言書の要件を満たさない場合や、遺言書の内容に問題がある場合もあり、実際に無効になった遺言書もほとんどが自筆証書遺言です。
また、公正証書遺言ですと、相続発生後に、遺言書の検認という裁判所を通した手続きをする必要がないため、スムーズに相続手続きを行うことができます。
そのため、「相続人の一人に全財産を相続させる」といった簡単な内容の遺言書でない限り、公正証書遺言をおすすめします。
特に、遺言書を手書きで書けないという場合には、公正証書遺言が良いでしょう。
参考リンク:遺言が書けない場合についてのQ&A
3 実際に作成する
ここからは、実際に遺言書を作成するまでの手順を、自筆証書遺言と公正証書遺言とに分けてご説明します。
⑴ 自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言を作成する場合は、紙とペンがあれば作成することができます。
自筆証書遺言の場合、①財産目録以外の全文を手書きし、②作成日を書き、③署名し、④最後に押印すれば完成です。
財産目録については、法律が改正され、パソコンで作成したものや通帳のコピーなどでも可能になりました。
財産目録を付ける際は、1ページごとに署名、押印が必要になりますので注意しましょう。
なお、自筆証書遺言保管制度を利用する場合は、所定の用紙のサイズ等がありますので、保管制度をご利用される方は、一度、専門家にご相談ください。
⑵ 公正証書遺言の場合
公正証書遺言を作成する場合、遺言を作成する人(遺言者といいます)の戸籍謄本、印鑑登録証明書、遺産を受け取る人の戸籍謄本又は住民票、通帳のコピーなどの財産関係が分かる資料を用意します。
その後、公証役場に連絡し、遺言の内容、遺言書作成の日にち等を調整します。
参考リンク:日本公証人連合会・公証役場一覧
公証人と遺言の内容について打ち合わせができましたら、実際に遺言書を作成することになります。
実際に作成する際は、遺言者が公証人に遺言の内容を簡単に説明し、公証人がすでに出来上がっている遺言書の内容を遺言者及び証人2人に読み上げます。
読み上げた遺言書に問題がなければ、遺言者及び証人2人が署名、押印し、遺言書が完成します。
公正証書遺言の作成費用についてはこちらをご覧ください。4 遺言書を保管する
自宅等で遺言書を保管する場合は、紛失のおそれがあるため、金庫等で保管しましょう。
なお、公正証書遺言の場合、原本が公証役場で保管されるため、紛失した場合であっても再発行をしてもらうことが可能です。
また、自筆証書遺言を法務局に預けた場合は、原本は法務局で電子データとして保管されるため、紛失のおそれはありません。
5 少しでも遺言書作成に不安を感じたらご相談を!
このように、遺言書を作成する過程で、いくつもの落とし穴や注意点が存在します。
そのため、遺言書作成に少しでも不安を感じた方は、お気軽に専門家にご相談ください。
私たちも、遺言に関するご相談を原則として相談料無料でお伺いしております。
また、すでに作成された遺言書の内容に法的問題点がないか等について、無料でアドバイスさせていただくサービスとして遺言書の無料診断も行っておりますので、ぜひ、ご活用ください。