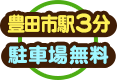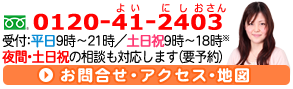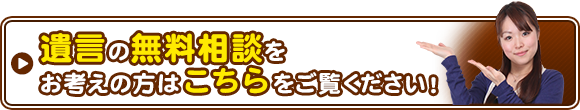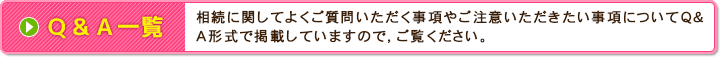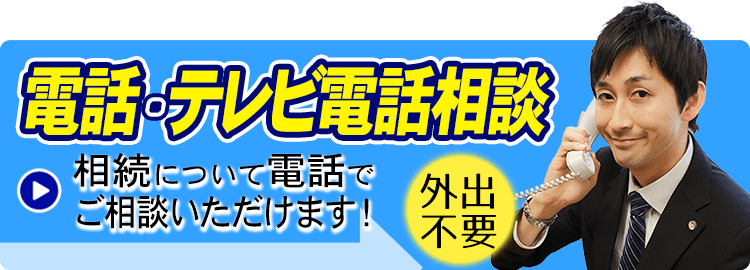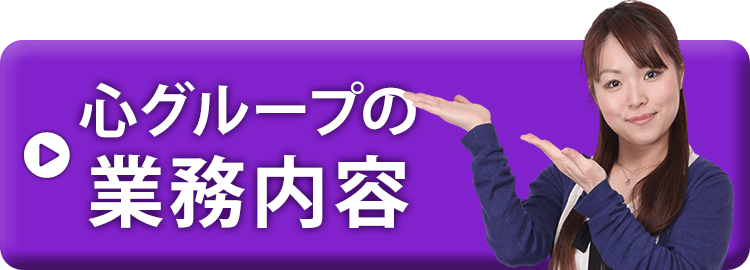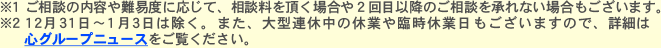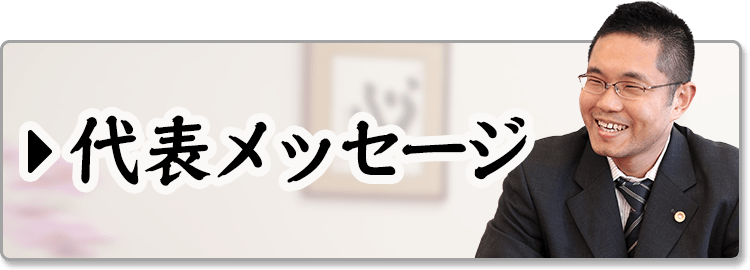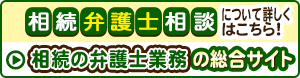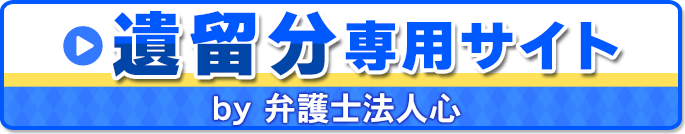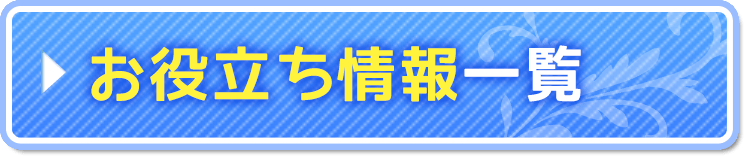遺言がある場合の相続について
1 自筆証書遺言が発見された場合
被相続人のご自宅などから自筆証書遺言が発見された場合は、すぐに家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。
参考リンク:裁判所・遺言書の検認
検認の手続きとは、簡単にいうと、裁判官の面前で、他の相続人の立ち合いのもと、遺言書の内容を確認する手続きのことです。
検認手続きを行う裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
検認手続きの際には、戸籍や収入印紙等が必要になります。
検認手続きについて不明な点などがある場合には、お気軽にご相談ください。
なお、検認を行わずに遺言を放置してしまった場合や、封がしてあるのに自分で開封してしまった場合は、5万円以下の過料が科せられてしまう可能性がありますので注意が必要です。
また、自筆証書遺言が法務局に保管されていた場合は、上記のような検認手続きは不要となります。
参考リンク:法務省・自筆証書遺言書保管制度
2 公正証書遺言が発見された場合
公正証書遺言の場合、遺言書の原本自体は公証役場に保管されます。
保管期間は、遺言者の死後50年、公正証書遺言の作成後140年または遺言者の生後170年の間とされています。
公正証書遺言は、相続人であれば、遺言者が亡くなっており、かつ、昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言であったときに遺言書を取得することができます。
取得の手続きの流れとしては、全国どこでもよいので、最寄りの公証役場まで行っていただき、遺言書がどこに保管されているのかを検索してもらい、取得していくことになります。
検索してもらう際に必要な書類は、①除籍謄本や戸籍謄本など、被相続人が死亡したことを証明する資料、②検索したい方が相続人であることを証明する資料、③検索したい方の運転免許証などの本人確認資料です。
公正証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認の手続を行う必要はありませんので、手続きが簡単です。
3 遺言の執行
自筆証書遺言の場合は検認終了後、公正証書遺言の場合はその存在が分かった後に、遺言書の内容を執行する手続きになります。
遺言のなかで遺言執行者が指定されていれば、預貯金の解約などの手続きはすべて遺言執行者が行ってくれます。
遺言執行者が指定されていない場合は、相続人全員で手続きを行うか、裁判所で遺言執行者を選んでもらう手続きが必要になります。
参考リンク:裁判所・遺言執行者の選任
相続人の負担を考えると、なるべく遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。
なお、遺言執行者は、相続人への通知、財産目録の作成、登記手続き、銀行への解約手続き等のことを行わなければいけません。
そのため、遺産や相続人が多い場合は、弁護士などを遺言執行者に選んでおくとよいかと思います。