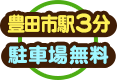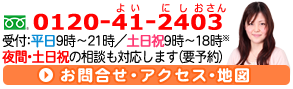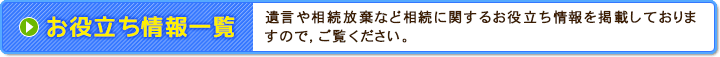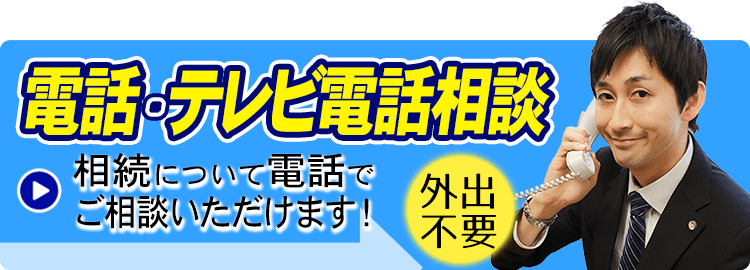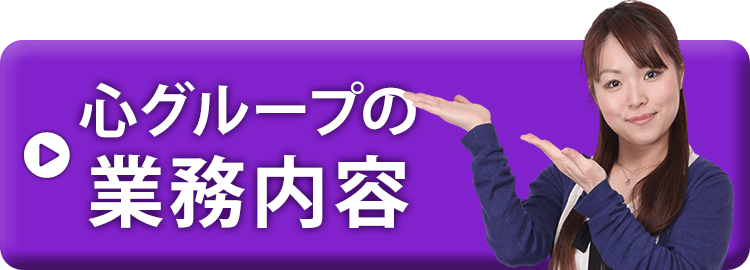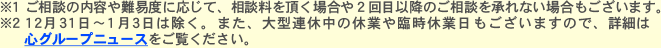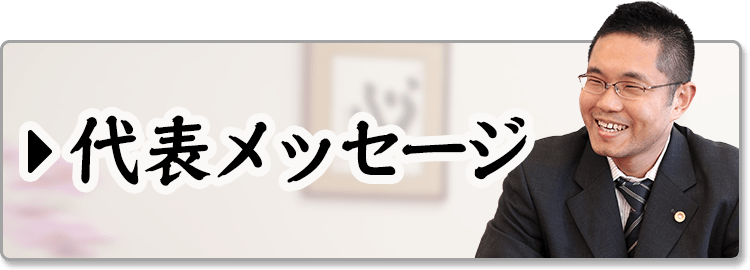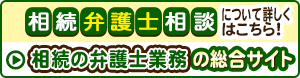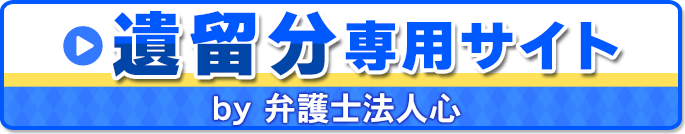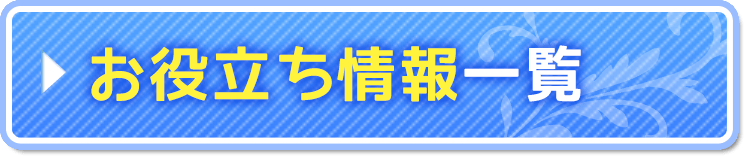法定相続情報証明制度に関するQ&A
法定相続情報証明制度とはどのようなものですか?
法定相続情報証明制度は、誰が相続人になるかといった相続関係を示した一覧図を法務局の登記官が認証する制度です。
裏付け資料として、戸除籍謄本等の束を登記所に提出する必要があります。
その後、法務局から、「法定相続情報一覧図の写し」が発行されます。
参考リンク:法務局・「法定相続情報証明制度」について
法定相続情報一覧図の発行は手数料がかかりますか?
法務局に支払う手数料はありません。
無料で発行してもらうことができます。
法定相続情報一覧図は何枚発行してもらえますか?
何枚でも発行してもらうことができます。
法定相続情報一覧図は何に使いますか?
不動産の相続登記、銀行口座や証券口座の相続財産調査や解約・名義変更手続き、死亡保険金の請求、遺族年金の請求、相続税の申告などに使います。
法定相続情報一覧図を使うメリットはありますか?
法定相続情報一覧図の申請や発行に費用がかからないこと、複数の相続手続きを同時に進めることができること、金融機関等が手続きを行う際に戸籍等を全て確認して相続人を特定する手間が軽減されること、提出した法定相続情報一覧図は、申出日の翌年から5年間、法務局で保管されるため、5年間は何度でも再発行が可能なことが挙げられます。
法定相続情報一覧図を使うデメリットはありますか?
法務局に申請するために相続関係図を作成しなければならず、その作成に手間と時間がかかること、作成には法務局が定める所定のルールがあること、申請者が戸籍謄本の収集をしなければならず、その手間を省略できるわけではないこと、相続手続きが少ない場合は作成の手間に比べてあまり利用価値が高くない場合があることなどが挙げられます。
法務局に申請するための相続関係図はどのように作ればよいですか?
様式は家系図のような「図形式」と、名簿のような「列挙形式」があります。
図形式の方が、一覧性が高く、一般的かもしれません。
図形式の作成方法はどのようなものですか?
用紙は、A4サイズの白い紙を縦長に使用します。
被相続人は、氏名、最後の住所、出生年月日、死亡年月日を記載します。
最後の住所は住民票の除票(または戸籍の附票)をもとに記載します。
最後の本籍地を記載することもできます。
相続人は、氏名、生年月日、被相続人から見た続柄を記載します。
住所を記載することもできます。
あとは、申請者本人もしくはその代理人を申出人として記載します。
法定相続情報一覧図の写しが発行されるまでどのくらいかかりますか?
法定相続情報一覧図の写しが発行されるまで、一般的には、申出から1〜2週間ほどかかることが多いです。
すぐに発行されるわけではないため、早めに作成することが重要です。
数次相続の場合はどのように法定相続情報一覧図を作成しますか?
数次相続の場合は、被相続人2名分の相続関係を一つの法定相続情報一覧図にまとめることはできません。
被相続人の死亡順に、それぞれの被相続人の二つの法定相続情報一覧図を作成する必要があります。
被相続人や相続人の住所を法定相続情報一覧図に記載する必要はありますか?
法定相続情報一覧図には、被相続人の住所は必ず記載しなければなりません。
他方で、相続人の住所についての記載は任意となっています。
もっとも、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載しない場合、相続人の居住地を証明できないため、不動産の相続登記や遺言書の検認手続きなどをする際に、別途、住民票や戸籍の附票、住民票記載事項証明書といった相続人の住所を証明する書類の提出が必要になってしまいます。
法定相続情報一覧図を作成したのに、結局追加で書類を取得しなければならなくなってしまうため、かえって手間となる可能性があります。
そのため、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載することで、別途必要書類を取得する必要がなくなりますので、もし名義変更や解約などの手続きが必要な財産が複数あるのであれば、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するのがよいでしょう。
土地の使用貸借があった場合の相続に関するQ&A Q&Aトップへ戻る