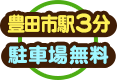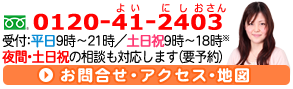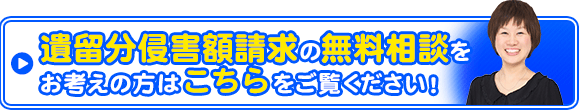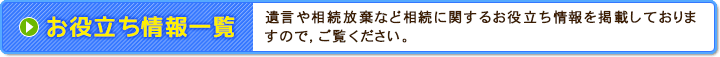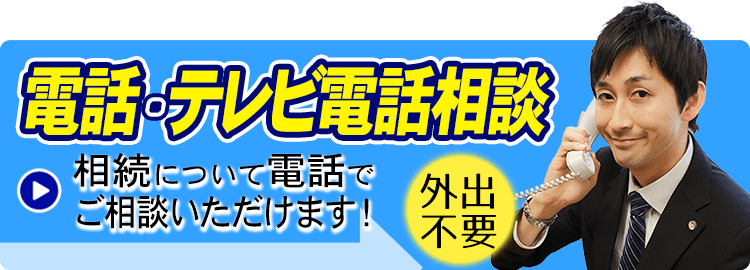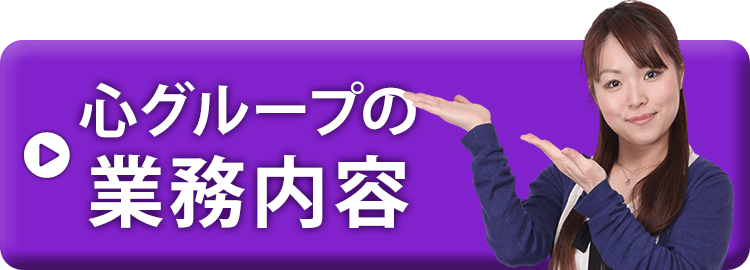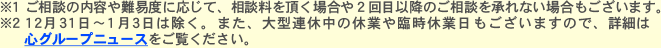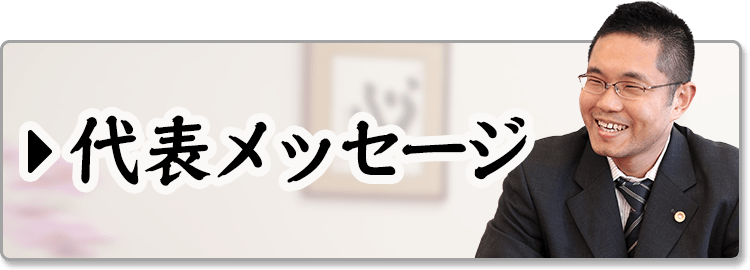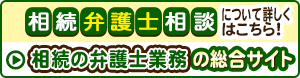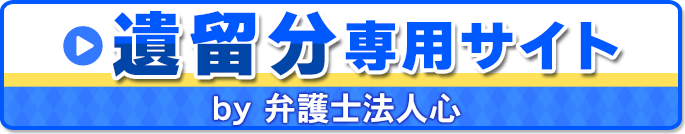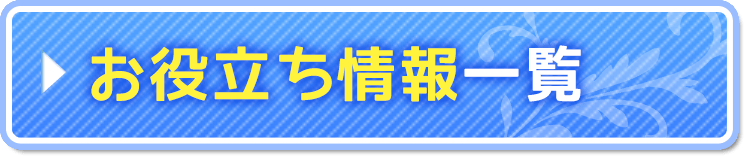生命保険と遺留分に関するQ&A
生命保険を活用すれば、遺留分対策になると聞いたのですが、どのような仕組みか簡単に教えてもらえますか?
まず、遺留分とは、相続人が相続について有する最低保障のようなもので、たとえ遺言書で「相続財産を全く渡さない」と記載しても、遺留分として、いくらかの金銭は受け取ることができます。
この遺留分の権利は、基本的に遺産総額(一部の生前贈与を含む)を基準として、遺留分の額が決まります。
そのため、遺産総額を少なくすれば、その分、遺留分額も減らすことができます。
そして、ここで活躍するのが生命保険です。
生命保険は、基本的に遺産には含まれないため、ご生前中に、財産を保険に変えておけば、遺留分の額を少なくすることができます。
遺留分対策で生命保険を使った方が良い場合の具体例は、どのようなものがありますか?
「遺産のほとんどが土地や建物の場合」「相続人の仲が悪い場合や疎遠な場合」は、生命保険を使って、遺留分対策をしておいた方が良いでしょう。
もっとも、遺留分の額を減らしたい場合は、基本的に保険を活用することをおすすめします。
1 遺産のほとんどが土地や建物の場合
遺留分は、現在、法律が改正され、お金を請求することができるという権利に変わりました。
遺留分の請求額は、土地や建物を含めた遺産相続から計算されます。
そのため、遺産に預貯金があまりなく、ほとんどが土地や建物などの不動産の場合、遺産を受け取った人は、自身のポケットマネーから遺留分を支払う必要が出てきます。
⑴ 保険を活用しなかった場合の具体例
例えば、預貯金が900万円、不動産の価格が3000万円で、遺留分が遺産の4分の1の975万円の場合で考えてみます。
この場合、遺産を取得する人は、遺留分を請求する人に対して、預貯金の900万円以外に、さらに75万円を手持ちの現金から支払う必要があります。
⑵ 保険を活用した場合の具体例
他方、このケースで900万円を全て生命保険に変えていた場合はどうなるでしょうか。
結果としては、遺産総額が不動産の3000万円のみとなり、遺留分額は750万円となります。
この場合、保険金から遺留分を支払っても、遺産を取得した方は、150万円が手元に残ります。
このように遺産のほとんどが不動産の場合は、遺留分を活用することで、遺産を取得する側が困らないようにすることが可能です。
2 相続人の仲が悪い場合や疎遠な場合
相続人の仲が悪い場合や疎遠な場合は、遺留分を巡って非常にもめる場合があります。
その際、生命保険を活用しておけば、いままでお話した通り、遺留分の額を大幅に減らすことも可能です。
また、相続開始後、すぐに保険の中から遺留分の支払いに充てることができるため、遺言書の検認や預貯金の解約等の面倒な手続きを省くことができ、早期の紛争解決につながります。
実際、遺留分対策をしている方の多くが、保険を活用されています。
そのため、相続人の仲が悪い場合や疎遠な場合は、遺留分対策として生命保険を活用されることをおすすめします。
遺産が預貯金しかなく、それを全て保険に変えてしまえば、遺留分は支払わなくても良いのでしょうか?このような遺留分対策は問題がないか教えてください。
遺産のすべてを保険に変えてしまっても、遺留分が発生します。
原則、保険は遺産には含まれないため、遺留分対策として有効です。
ただし、保険の額が遺産の額に比して、極めて多い場合は、例外的に保険の額も遺産に準じて、遺留分の対象になることがあります。
実際、過去に裁判で争われた事例では、保険金も遺産に準じたものとして判断されてしまった事例もあります。
そのため、遺留分対策で保険を活用する場合は、一度、専門家に「どのぐらいまでなら保険にしてよいのか」について、ご相談することをおすすめします。
遺留分対策を相談する場合、どの専門家にご相談すれば良いのでしょうか?
相続に詳しい専門家であり、かつ、保険についてもアドバイスをしてくれる専門家にご相談されることをおすすめします。
遺留分対策は、過去の裁判例や相続の詳しい知識、どのような保険が適切なのかの知識が要求されます。
一歩間違えると、遺留分対策が失敗に終わる可能性もあります。
例えば、保険をいくらまでなら入っても良いのかを知らなければ、十分な遺留分対策になるとは限りません。
そのため、遺留分対策をご相談される際は、裁判実務に精通しており、かつ、保険の種類等、保険に関しても相談できる専門家にご相談されることをおすすめします。
相続放棄時の遺品整理に関するQ&A 遺留分放棄に関するQ&A