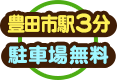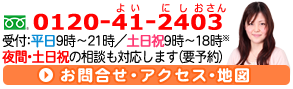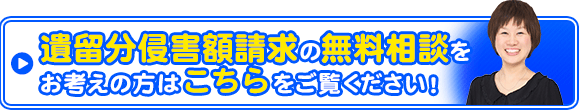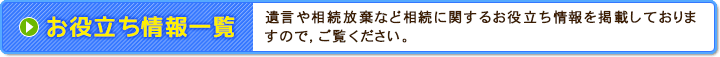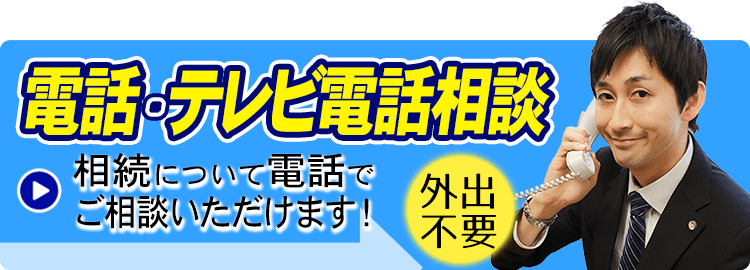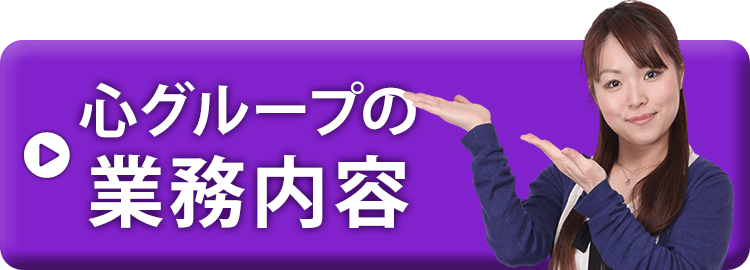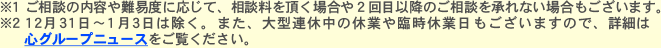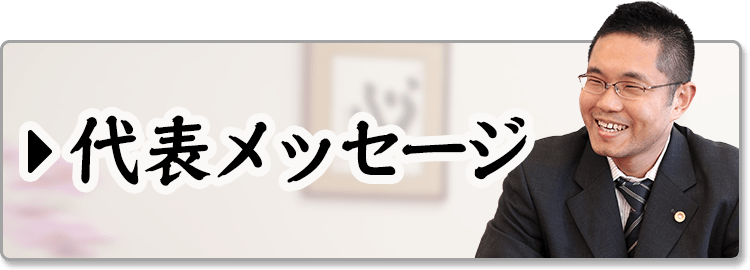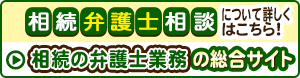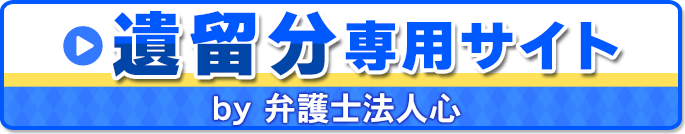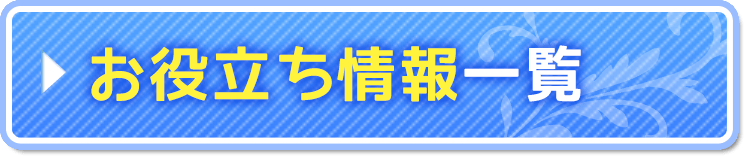遺留分放棄に関するQ&A
遺留分放棄とはどのような制度ですか?
遺留分放棄とは、遺留分の権利を放棄することをいいます。
遺留分放棄には、被相続人(相続の対象となる人)の生前に行うものと、死後に行うものとがあります。
このうち、生前の遺留分放棄では、家庭裁判所の許可がない限り、効果が生じません。
そのため、口頭で遺留分の放棄をした場合でも、家庭裁判所の許可を得ていない限り、被相続人の死後、遺留分を請求することができる可能性があります。
他方、死後の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可は不要です。
そのため、書面だけでなく、口頭でも遺留分を放棄することができます。
なお、遺留分放棄は、遺留分を放棄したい相続人が行う制度です。
被相続人が特定の相続人に対し、遺留分の権利を放棄させる制度ではありませんので、ご注意ください。
遺留分放棄と相続放棄とでは何が違うのですか?
遺留分放棄と相続放棄の大きな違いとして、遺留分放棄の場合、相続の権利は放棄していませんので、遺留分を放棄した後であっても、遺産分割に参加し、遺産を取得することができます。
これに対し、相続放棄をしてしまうと、遺留分も含めた権利を放棄することになります。
他の違いとしては、遺留分放棄は、家庭裁判所の許可を得れば、生前に行うことができますが、相続放棄はそのような制度はなく、生前に相続放棄をすることはできません。
生前の遺留分放棄の具体的な方法を教えてもらえますか?
生前の遺留分放棄は、必要書類を集めて、遺留分を放棄する人が被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に書類一式を提出します。
集める書類としては、基本的に、申立書、財産目録、被相続人の戸籍謄本、遺留分放棄をする人(申立人)の戸籍謄本、800円の収入印紙、切手が必要になります。
遺留分放棄の許可の申立書は、裁判所のホームページからダウンロードできます(参考リンク:裁判所・遺留分放棄の許可の申立書)。
これらの書類に加えて、裁判所より追加で書類を提出するよう、指示されることもあります。
書類提出後、特に問題なければ、裁判所より遺留分放棄を認める審判が出されます。
また、内容次第では、直接裁判官と話をする審問という手続きが行われることもあります。
なお、遺留分放棄が認められなかった場合、一定の期間内であれば、不服申立てを行うこともできます。
どういった場合に生前の遺留分放棄が認められますか?
遺留分放棄が認められるためには、以下の3つの要件を満たしている必要があり、どれか一つでも欠けてしまうと、遺留分放棄が認められない可能性があります。
① 遺留分放棄が申立人の自由意思であること(本人の自由意思)
② 遺留分放棄の理由に合理性と必要性があること(放棄理由の合理性・必要性)
③ 遺留分放棄に見合うだけの見返りがあること(放棄の代償)
それぞれについて、詳細を説明いたします。
- ① 本人の自由意思について
-
遺留分放棄が被相続人や親族に脅されて行われたものである場合、遺留分放棄は認められません。
もっとも、被相続人や親族に説得されて、遺留分放棄を自ら行う場合は、問題ありません。
- ② 放棄理由の合理性・必要性について
-
遺留分放棄の理由について、遺留分放棄をすることがもっともであり、必要がある場合に、この要件が認められます。
- ③ 放棄の代償
-
遺留分放棄を行う以上、それに見合った代償を被相続人から渡されている必要があります。
たとえば、被相続人から遺産の2割に当たる財産の生前贈与を受けていたケースなどです。
遺留分放棄について相談できますか?
はい、ご相談いただけます。
上記のように、遺留分放棄を行う場合、各要件について検討し、裁判所に遺留分放棄を認めてもらう必要があります。
その際、裁判所への伝え方次第で、遺留分放棄ができるかどうかが変わってくる場合もありますので、遺留分放棄をするかお悩みの方は、私たちにご相談ください。
遺留分をはじめ、相続に関する案件を得意とするものが対応させていただきます。
生命保険と遺留分に関するQ&A 相続税の税務調査についてもお願いできますか?