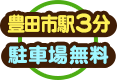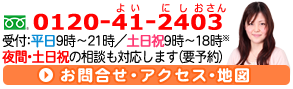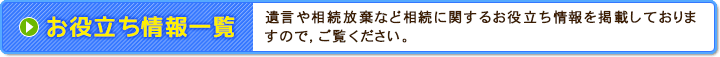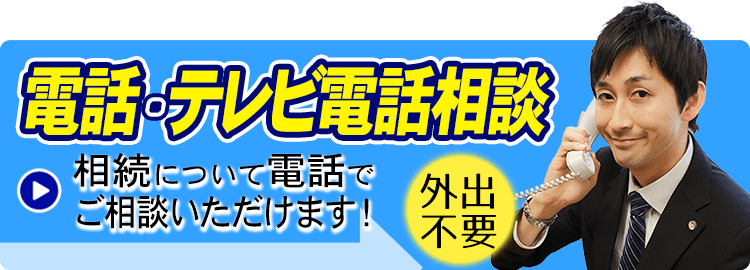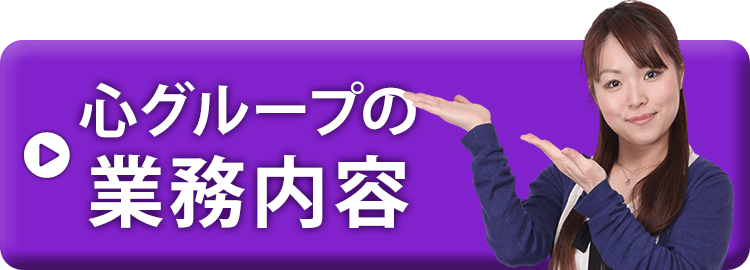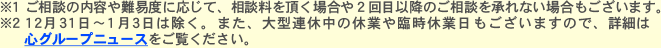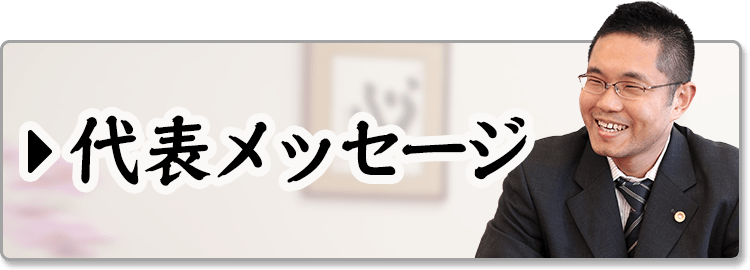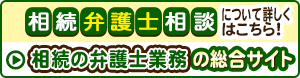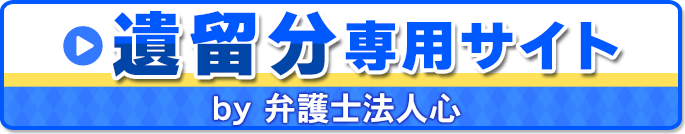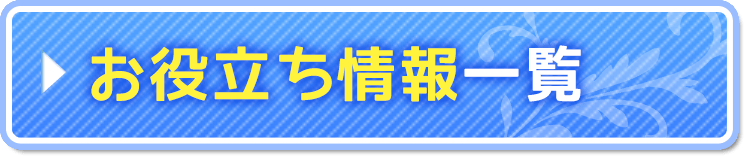法定相続人がいない場合のQ&A
法定相続人がいない場合、遺産はどのようになりますか?
法定相続人がいない場合、受遺者や債権者、特別縁故者等の有無よっても異なりますが、これらの受遺者等がいない場合には、最終的に国に帰属します。
なお、令和3年では、国庫に帰属された遺産は647億円にのぼり、過去最高額となりました。
そもそも、法定相続人がいない場合とは、子や両親、兄弟姉妹がおらず相続人がいない場合はもちろん、相続人全員が相続放棄をした場合も含まれます。
法定相続人がいない場合でよくあるケースとしては、独り身の方が亡くなった場合や、亡くなった方(被相続人といいます)が借金を抱えていたため、相続人全員が相続放棄をした場合などがあります。
法定相続人がいない場合、その後の手続きはどのようになりますか?
法定相続人がいない場合、遺言の有無や内容等によっても異なりますが、基本的には、家庭裁判所を通して相続財産清算人を申し立てる必要があります。
相続財産清算人の役割としては、債権者や受遺者(遺言書で財産を取得する人)等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させることです。
相続財産清算人が選任された後は、相続財産清算人が選任されたことを知らせるための公告及び相続人を捜すための公告や、相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告、特別縁故者に対する相続財産分与の申立て、遺産の換価等を行います。
その結果、遺産がなおも残存する場合は、国に帰属します。
なお、遺言書があり、その内容が相続財産すべてを遺贈するという内容であり、かつ、遺言執行者も選任されている場合は、基本的に相続財産清算人を選任することなく、預貯金の解約や不動産の名義変更等を行うことができます。
もっとも、遺言書があっても、遺言執行者が指定されていない場合は、相続財産清算人を選任するか、裁判所を通して遺言者執行者を選任してもらう必要があります。
遺言書がない場合や、遺言書があっても特定の財産を遺贈するという内容である場合は、家庭裁判所を通じて相続財産清算人を選任してもらう必要があります。
相続財産清算人が選任された後、国庫に帰属されるまでにどのぐらいの日数がかかりますか?
遺産の内容や受遺者や債権者の数、特別縁故者の有無等によっても異なりますが、最低でも1年以上かかることがほとんどです。
理由として、相続財産清算人が選任されたことを知らせるための公告及び相続人を捜すための公告だけでも6か月の期間を置く必要があり、遺産の換価についても、裁判所の許可が必要になるなど、手続きとしても複雑かつ時間がかかるものであるためです。
相続財産清算人を選任する手続きを教えてください
- 1 申立ができる人
-
まず、相続財産清算人は、相続放棄をした相続人、被相続人の債権者、受遺者、特別縁故者(被相続人の面倒等を看ていた人など)が選任を申し立てることができます。
- 2 必要書類
-
申立に必要な書類としては、少なくとも以下の書類が必要になります。
・被相続人が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本
・被相続人の両親が生まれてから現在までの一連の戸籍謄本
・被相続人の住民票または戸籍の附票
・被相続人の財産関係を証明する書類(登記事項証明書、預貯金通帳、固定資産税課税証明書等)
・申立人の利害関係を証明する資料(相続放棄をした相続人の場合は、相続人の戸籍謄本及び相続放棄申述受理通知書等)
・収入印紙800円
・郵便切手(裁判所ごとに異なります。)
・官報公告料5075円
なお、以下の裁判所のホームページにも相続財産清算人選任申立の必要書類等が記載されておりますので、あわせてご確認ください。
参考リンク:裁判所・相続財産清算人の選任
- 3 申立先
-
相続財産清算人を選任する場合は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に上記の書類を提出することになります。
被相続人の最後の住所地が豊田市の場合は、名古屋家庭裁判所岡崎支部に申し立てることとなります。
- 4 予納金
-
相続財産清算人を選任した後、裁判所から予納金を納めるように連絡がくる場合があります。
予納金とは、相続財産清算人の報酬等に使われる費用であり、予納金の額は、遺産の額や内容等によっても異なりますが、通常は50万円~100万円前後する場合があります。
予納金は、遺産に預貯金等の財産がある場合は、予納金を支払わなくても良い場合もあります。
実際の予納金の金額については、事前に裁判所に確認されることをおすすめします。
相続登記だけでもお願いできますか? 遺言が書けない場合についてのQ&A