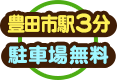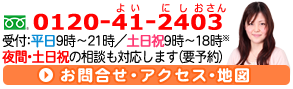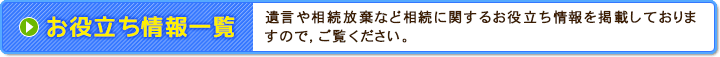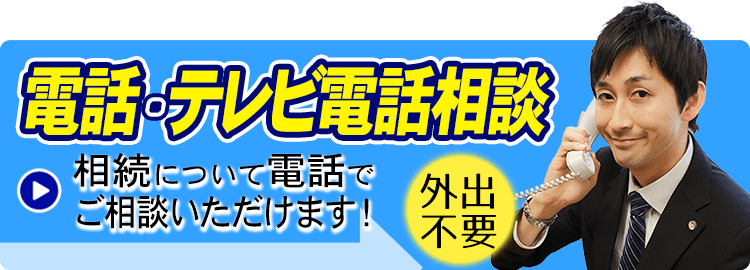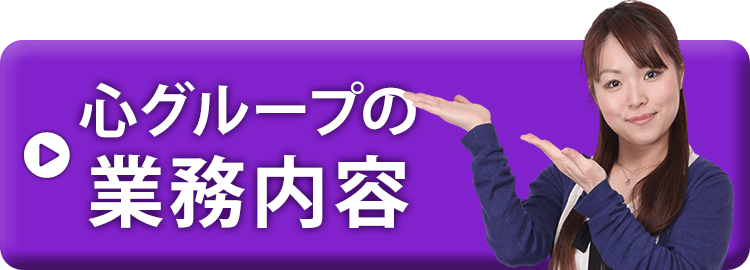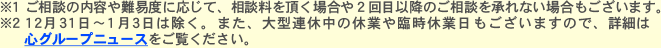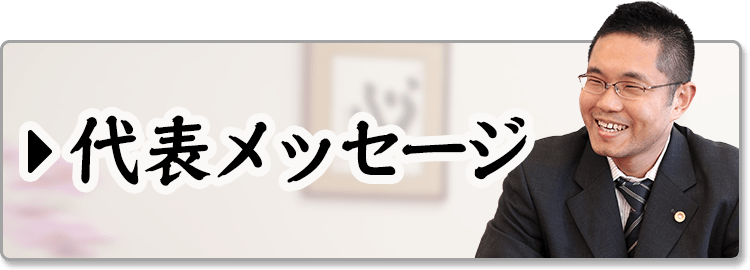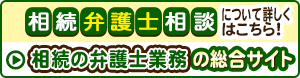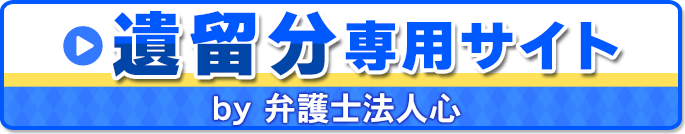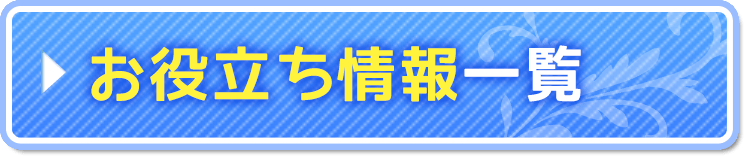土地の使用貸借があった場合の相続に関するQ&A
長男は、父から土地を無償で借り、そこに家を建てて住んでいます。父が亡くなった場合、長男が土地を無償で借りていることについて、他の相続人は、何か主張できることはありますか?
被相続人の父から、土地を無償で借りている相続人の長男には、特別受益が認められ、その分、長男が相続する額が少なくなる場合があります。
特別受益を考慮した遺産分割がなされることで、公平に財産を分けることができます。
1 特別受益とは
そもそも、特別受益とは、簡単に言うと、被相続人から相続人に対する、生前贈与などの財産の前渡しのことをいいます。
たとえば、生前に親が子に家を建てるためにお金を贈与した場合や、土地を贈与した場合などに、特別受益として認められる場合があります。
この特別受益が認められた場合、利益を受けた相続人は、その特別受益の額だけ、相続する額が少なくなります。
2 土地の無償使用(使用貸借)の場合
被相続人から土地を無償で借り、その上に建物を建てている相続人は、被相続人から、土地を無償で借りる権利を渡されたと考えることができます。
この権利のことを、使用貸借権といいます。
そのため、利益を得た相続人には、使用貸借権の金額分、特別受益が認められる場合があります。
一般的に、使用貸借権の価格は、土地の価格の10%から30%と言われています。
今回のケースに当てはめて考えると、長男が取得した使用貸借権の価格が500万だとすると、長男は、500万円分、相続で取得する額が少なくなる場合があるということになります。
なお、土地を無償で借りていることについて、土地の地代相当額を特別受益として主張される場合がありますが、基本的には、使用貸借権分のみを特別受益として考えられています。
長男は、父から土地を借りて、家を建てています。しかし、父は、長男との仲が良くなく、貸している土地から出て行って欲しいと考えていました。この場合、父が亡くなった後に長男を追い出すことは簡単ですか?
長男が父から無償で土地を借りている場合、簡単に長男を追い出すことはできません。
父が長男に使用貸借していた状態が、父の相続人にも引き継がれるため、基本的に、親族間の使用貸借は、他人との使用貸借と異なり、すぐに貸したものを返してもらうことはできませんので、今回のケースで長男を追い出す場合は、裁判を起こさなければならないかもしれません。
また、裁判を行なった場合でも、長男が土地を使用している期間が20年以内だと、追い出すことが難しくなります。
さらに、長男が建てた建物の構造(鉄骨造か木造か)や父が長男に土地を貸した経緯によっては、30年以上経過しても、追い出すことができない場合もあります。
このように、親族間の使用貸借については、強力な権利が発生するため、無償で使用させる場合は、ご注意ください。
また、地代相当額を請求しようにも、使用貸借権が認められてしまうと、地代も請求できない可能性があります。
親から土地を無償で借りる場合、贈与税や相続税で問題になりますか?
親から土地を無償で借りる場合、贈与税はかかりません。
税金関係において、個人間の使用貸借権の価値は、ないものとして考えられるからです。
そのため、土地を無償で貸している場合であっても、借主に贈与税はかかりませんし、相続税の課税対象にもなりません。
詳細については、以下の国税庁のホームページもご参照ください。
※参考リンク:使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて
なお、賃貸借の場合は、相続税等が発生する場合があります。
相続人と連絡が取れない場合についてのQ&A 法定相続情報証明制度に関するQ&A