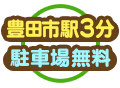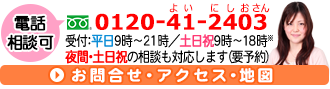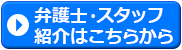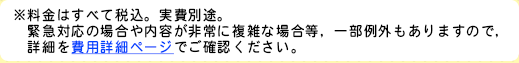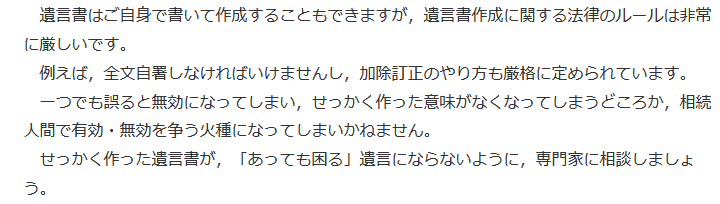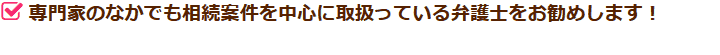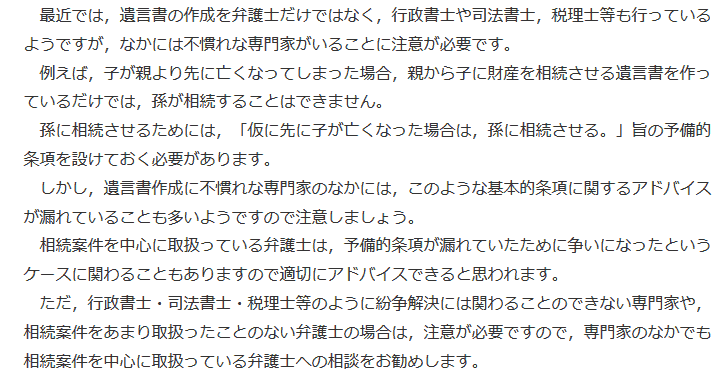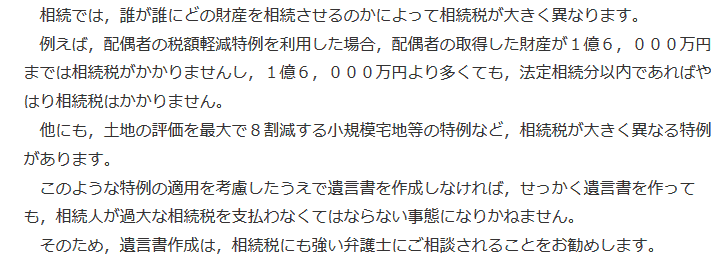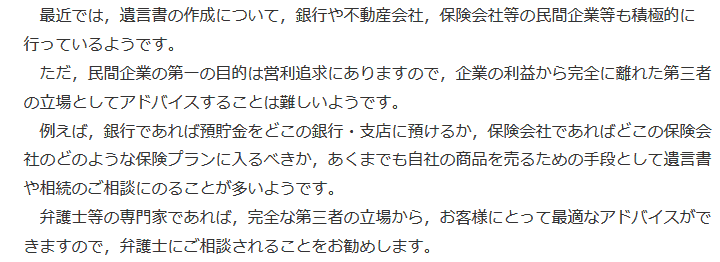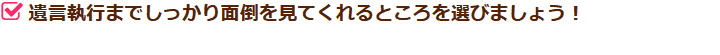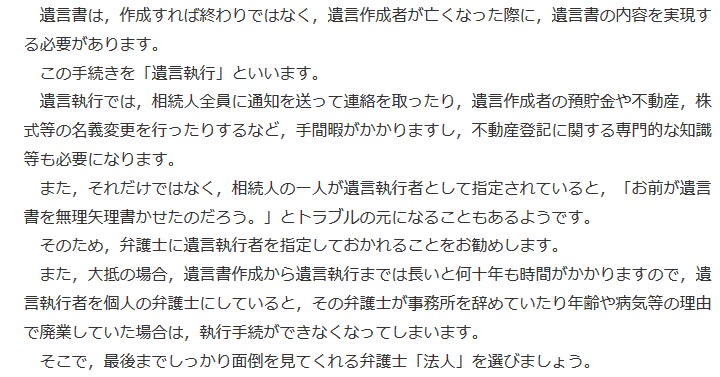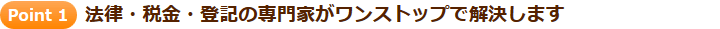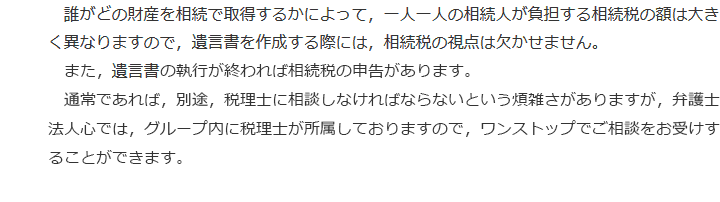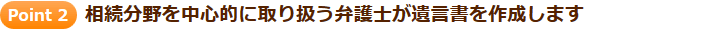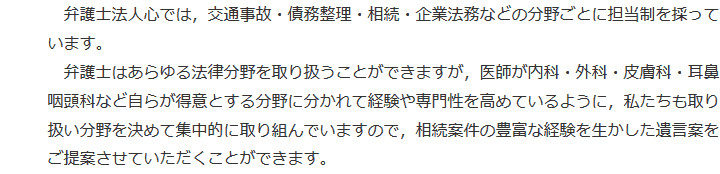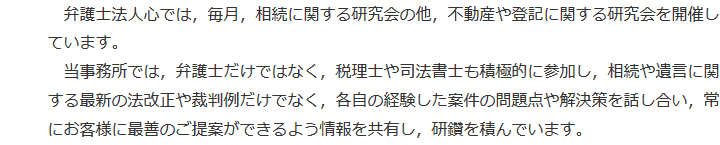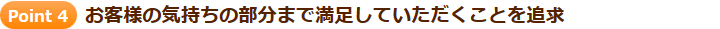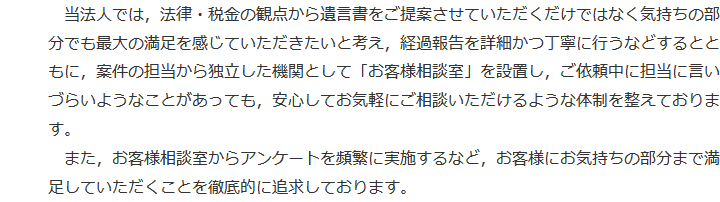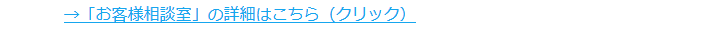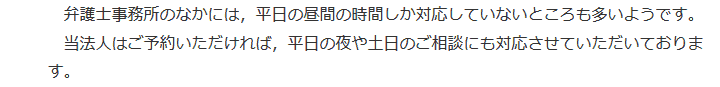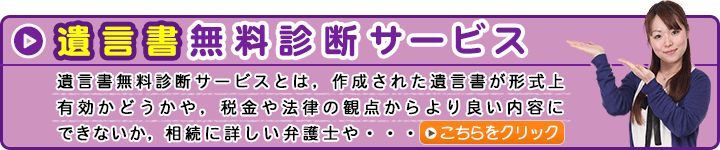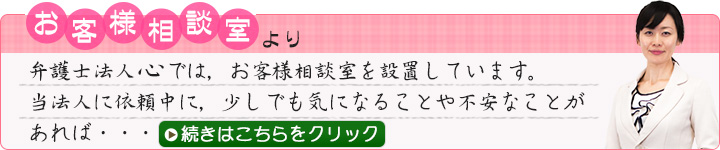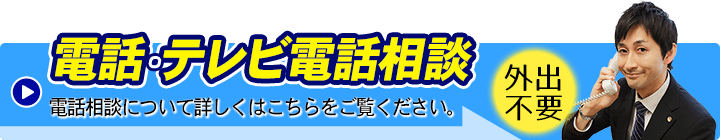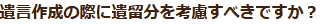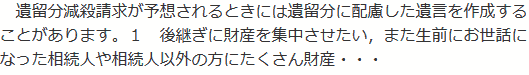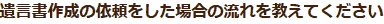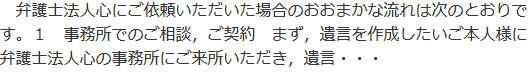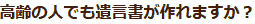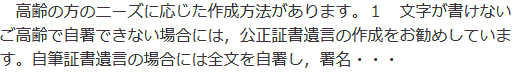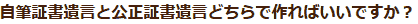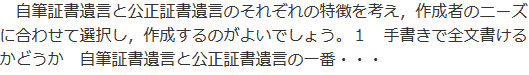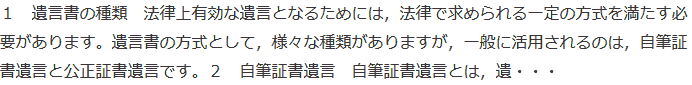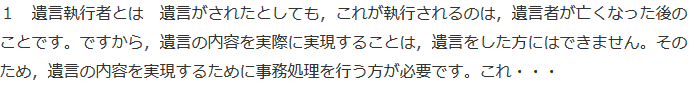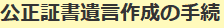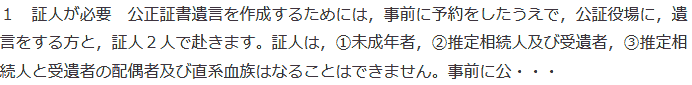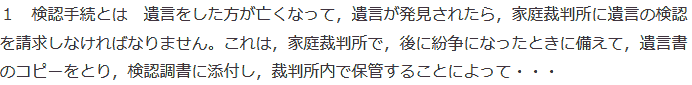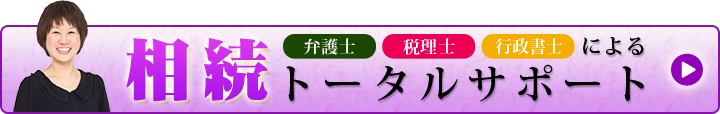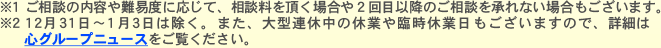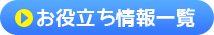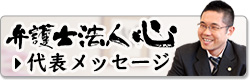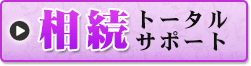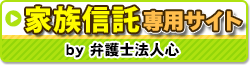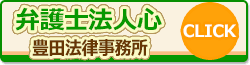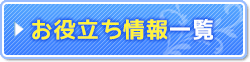遺言に関するご質問
豊田にお住まいで遺言を残したいとお考えの方の中には様々な疑問が生じているという方もいらっしゃるかと思います。こちらにQ&Aをご用意していますので、ご覧ください。
遺言をお考えの方はご覧ください
遺言に関する様々なお役立ち情報をまとめています。遺言をお考えの方、制度について知りたいという方は、ご覧ください。ご相談の際にも、弁護士が丁寧にお答えいたします。
相談しやすい事務所です
電車でも車でもアクセスしやすい場所に事務所があります。こちらから事務所所在地や駐車場の場所をご覧いただけますので、お越しの際にはご確認ください。
遺言を作っておくべき場合
1 相続人が複数いるケース

基本的に、相続人が複数いる場合は、遺言を作っておくべきです。
遺言を作成されていない方の中には、「相続人みんな仲が良いため、揉めるはずはない」「揉めるほどの遺産がないから大丈夫」と考えている方もいます。
しかし、実際に、「あれほど仲が良かった姉妹が、遺言がないばかりに、相続で揉め、姉妹の子や孫の代も含めて、絶縁状態になってしまったケース」や、「遺産が400万円ぐらいだが、解決までに3年以上かかったケース」もあります。
どんなに相続人の仲が良いケースでも、当該相続人の配偶者など、相続人以外の人が原因で揉めるケースも多々あります。
また、遺産分割調停や審判といった裁判手続きになるケースの大部分が、遺産が5000万円以下のケースであり、遺産が少なければ揉めないという訳ではないといえます。
そのため、相続人の仲が良くとも、また、遺産が少額と思っていたとしても、相続人間で揉めてしまうこともありますので、相続人が複数いる場合は、遺言書を作成しておいた方が良いでしょう。
2 相続人以外に遺産を渡したい場合
相続人以外の人に財産を渡したい場合は、遺言を作成しておいた方が良いです。
なぜなら、遺言がないと、相続人以外の人に遺産が渡らないためです。
また、そもそも相続人がいない場合は、一部の例外を除き、遺言がないと、遺産は最終的に国に帰属してしまいます。
そのため、お世話になった人や慈善団体に寄付をしたいなど、相続人以外に遺産を渡したい場合は、遺言を作成しましょう。
3 世代を超えて遺産を渡したい場合
たとえば、遺言があれば、自宅を子に相続させるのではなく、孫に相続させることもできます。
遺言がない場合だと、自宅は、まず子に相続され、子が亡くなってから孫に相続されることになります。
しかし、遺言があれば、世代を超えて遺産を相続させることが可能となります。
なお、本来の相続人以外に遺産を渡す場合、渡す遺産が不動産だと、相続人に渡す場合に比べて、税金面で不利になる場合もありますので、注意が必要です。
遺言執行に不安がある方へ
1 遺言執行者は誰にすべきか

未成年者と破産者でなければ、どなたでも遺言執行者になれます。
しかし、遺言執行者を誰にするかによって、遺言執行の完了時期や執行内容が異なることがあります。
遺言執行は速やかに行う必要があり、万一、対応が遅れてしまうと、本来は財産を受け取らない相続人に不動産を売られてしまったり、預貯金を一部払い戻されたりする場合があります。
また、遺言執行者は、法律に定められた義務を行わなければならず、万一、義務に違反してしまうと、相続人から損害賠償請求をされることがありますので、注意が必要です。
そのため、遺言書の内容を確実に実現したい方や、遺言執行にご不安な方は、遺言執行者に専門家を選ぶことをおすすめします。
2 遺言執行者の義務
遺言執行者の義務としては、遺言書の内容の開示、財産目録の作成、交付、相続人への報告、遺言の執行、遺言執行の完了の報告、精算等、多岐に渡ります。
また、遺言執行は、迅速に行う必要があり、万が一、遺言執行が遅くなってしまうと、相続人から損害賠償請求をされたり、遺言執行自体ができなくなったりする場合があります。
例えば、被相続人が父、相続人が長男と長女で、長男に全財産を渡す遺言書があった場合、長女は、遺留分は別として、遺産に関する権利がないため、父の預貯金を解約したり、不動産を売却したりはできないはずです。
しかし、遺言執行がなされる前であれば、長女としては、預貯金に関しては、1金融機関当たり、最大150万円までを引き出すことが可能な場合があり、不動産については、2分の1の権利について、他人に売却してしまうことができます。
万が一、そのような事態になってしまった場合、遺言執行者として責任を取らざるを得なくなるかもしれません。
3 遺言執行は相続を得意とする専門家にご相談を
このように、遺言執行に関しては、行うべき業務が多々あるだけでなく、万が一、迅速に執行ができないと、損害賠償請求の責任を負う場合があるなど、リスクも存在します。
そのため、遺言執行にご不安な場合や、遺言執行に不慣れな方は、一度、相続を得意とする専門家にご相談ください。
当法人では、遺言執行を数多く手がけてきた専門家による、遺言執行の無料相談も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
遺言を作成するタイミング
1 遺言の作成は手遅れになる前に

遺言を作成するタイミングとして、おすすめは、「早ければ早いほど良い」です。
なぜなら、いざ作成しようと思った時点では、認知症になってしまっているケースや、突然の事故で遺言書を作成したくても作成できなくなっているケースもあるためです。
実際、遺言書を作成しようと思ったが、認知症のため遺言書の作成ができなかったケースや、親に遺言書を書いてもらおうと思ったが、親が施設に入ってしまい、コロナのために会えず、遺言が作成できなかったケースもあります。
そのため、遺言を作成するタイミングは、早ければ早いほど良く、「いつ作成したらいいか」と悩むよりも、すぐに遺言書を作成した方がよいかと思います。
2 遺言は何度でも書き直すことができる
遺言は、基本的に何度でも書き直すことができます。
そのため、一度遺言を作ってみて、その後、環境の変化や家族構成の変化、お気持ちの変化等に沿って、遺言を書きかえることもできます。
また、手書きの遺言の場合、紙とペンさえあれば作成することができるため、それほど労力と時間もかかりません。
3 遺言の作成方法
遺言には、よく使われるものとして、手書きの遺言(自筆証書遺言といいます)と公証役場で作る遺言(公正証書遺言といいます)があります。
自筆証書遺言の場合、遺産目録を除く全文と、名前、日付を自書し、押印をすることで完成します。
公正証書遺言の場合、公証役場にどのような内容の遺言を作るのか調整し、実際に公証人と証人2名の立ち合いのもと、遺言を作ることになります。
どちらも長所と短所がありますが、費用がかからず、かつ、手軽なのは自筆証書遺言です。
他方、複雑な内容の遺言になると、全文を手書きで行うのもかなりの労力が必要になるため、その場合は公正証書遺言を利用した方がよいケースもあります。
私のおすすめとしては、一旦、簡単な内容でも大丈夫ですので、自筆証書遺言を作り、70歳を超えたタイミングや、病気になったタイミングで、公正証書遺言を作ることです。
このように行うと、万一のことがあったとしても、自筆証書遺言があるため、相続人間のトラブルを予防できたり、ご自身の遺志を尊重した遺産分配が可能になったりするためです。
遺言書は、適切なタイミングで作らないと、作れなくなる可能性もありますので、遺言の作成でお悩みの方は、簡単な内容でも大丈夫ですので、遺言を作成してみることをおすすめします。
どのように作成したらよいかわからないという方は、お気軽に弁護士にご相談ください。
遺言の種類
1 普通方式遺言と特別方式遺言

遺言には大きく分けて2種類あり、それぞれ普通方式遺言と特別方式遺言と呼ばれます。
多くの場合、普通方式遺言が使われており、その中でも自筆証書遺言および公正証書遺言がよく使われています。
特別方式遺言が利用されるケースは、ほとんどありません。
⑴普通方式遺言とは
普通方式遺言とは、簡単にいうと、日常生活の中で作成される普通の方式の遺言書のことです。
普通方式遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、秘密証書遺言が使われるケースはほとんどありません。
⑵特別方式遺言とは
特別方式遺言とは、通常の遺言書(普通方式遺言)を作成することが困難な状況の場合に利用できる特別な方式の遺言のことをいいます。
特別方式遺言には、危急時遺言(一般危急時遺言・難船危急時遺言)と隔絶地遺言(一般隔絶地遺言・船舶隔絶地遺言)があります。
このうち、実際に使われる可能性がある遺言は、一般危急時遺言です。
もっとも、一般危急時遺言も、自筆証書遺言や公正証書遺言に比べるとほとんど利用されません。
2 普通方式遺言の種類
⑴ 自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、手書きで作成する遺言書のことをいいます。
一般的な遺言書のイメージに一番合致するのが、この自筆証書遺言かと思います。
自筆証書遺言を作成する場合は、必ず、財産目録を除く全文を手書きし、日付を記入した後、署名、押印をする必要があります。
どれか一つでも欠けてしまうと、遺言書自体が無効になる可能性があります。
また、誤字、脱字があった場合の修正方法も、単純に二重線を引くだけでは足りず、どの箇所をどのように訂正したのかを記載のうえ、署名し、修正部分に押印する必要があるなど、非常に複雑なものとなります。
なお、自筆証書遺言については、法務局で保管してもらえる自筆証書保管制度ができました。
⑵ 公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言のことをいい、公証人と証人2人とともに作成する遺言のことをいいます。
公正証書遺言は、基本的に、公証役場で作成しますが、公証役場に行くことが難しい場合、公証人が施設やご自宅に出張して作成してくれる場合もあります。
また、公正証書遺言では、公証人が内容のチェックをしますので、自筆証書遺言に比べ、無効になる可能性が低いです。
もっとも、公正証書遺言であっても、認知症の方が作成された遺言ですと、認知症の程度によっては、遺言書自体が無効になってしまうため、注意が必要です。
公証人は基本的に、どのような内容の遺言書であれば税金が抑えられるかや、遺留分を少なくするためにはどのような方法がよいのか等についてアドバイスすることができません。
⑶ 秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、公証人と証人2人以上に遺言書の「存在」の証明をしてもらいながら、公証人、証人、相続人含め、本人以外は内容を見ることができない遺言のことを言います。
秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にすることができることに特色があります。
もっとも、公証人にも遺言内容を秘密にする必要はそれほどなく、手続きとしても煩雑であるため、ほとんど利用されません。
3 特別方式遺言の種類
特別方式遺言には、危急時遺言(一般危急時遺言と難船危急時遺言)と隔絶地遺言(一般隔絶地遺言と船舶隔絶地遺言)があります。
これらの遺言は、普通方式遺言ができない特殊な状況下において認められるものであり、ほとんど利用されることはありません。
また、特別方式遺言は、遺言者が普通方式での遺言ができる状態になってから6ヶ月間生存していた場合は、特別方式で作成した遺言は無効となります。
⑴ 一般危急時遺言
一般危急時遺言とは、病気等で死期が迫っている方が利用する遺言です。
例えば、末期がんで余命いくばくもないが、遺言書を残したいという方で、自筆証書遺言も作成することが難しい場合に利用されます。
方法として、3人以上の証人が必要となり、遺言書作成者(遺言者)が口頭で遺言内容を説明し、証人がそれを文章に書き起こます。
次に、筆記した証人が、遺言者と残りの2人の証人に対し、遺言の内容を読み聞かせて、筆記の内容が正確なものであることを承認します。
最後に、証人による署名押印をすることで遺言として成立します。
もっとも、注意点として、遺言書作成日から20日以内に裁判所に対して確認請求をしないと無効になります。
特別方式遺言の中では、使われる機会がある遺言です。
危急時遺言を検討するということは、緊急の状況である訳ですから、こちらとしても出来るかぎり丁寧に対応させていただきます。
内容を確認して、緊急的に対応が必要な場合には早急にご連絡をお願いします。
※危急時遺言の作成に必要な人数を集めることが、すぐには出来ない場合もあります。
⑵ 難船危急時遺言
船舶危急時遺言とは、船の遭難や飛行機の難航などの原因により、死が目前に迫っている状況で行う遺言です。
2人以上の証人のもとで、遺言者が口頭で遺言内容を説明し、それを文章に書き起こす必要があります。
証人はその場に立ち会っている必要はなく、口頭で遺言の内容を聴き取り、書面にまとめ、証人が署名、押印すれば問題ありません。
一時臨終遺言と違い20日以内という制限はありませんが、遅滞なく確認請求を受ける必要があります。
⑶ 一般隔絶地遺言
一般隔絶地遺言とは、伝染病での隔離されている場合や刑務所に服役中、災害に被災している場合など、死は迫っていないが自由に行動をすることができない状況で行う遺言です。
一般隔絶地遺言では、警察官1人と証人1人以上のもとで、遺言者本人が遺言書を作成する必要があり、本文を代筆することも可能です。
また、遺言者と、警察官、証人の署名・押印は必ず必要になります
なお、一般隔絶地遺言の場合、危急時遺言のように家庭裁判所による確認請求は不要です。
⑷ 船舶隔絶地遺言
船舶隔絶地遺言とは、船舶中で死は迫っていないが、船の中で遺言書を作成したい状況で利用できる遺言です。
船長または乗務員1人と証人2人以上のもとで、遺言者が遺言書を作成する必要がありますが、本文を代筆することも可能です。
この場合、船長または乗務員と証人の署名・押印が必要となります。
なお、一般隔絶地遺言と同様、家庭裁判所による確認請求は不要です。
遺言の作成で困った場合の相談先
1 遺言の作成を得意とする専門家にご相談を

遺言書の作成にお困りの方は、遺言書の作成を得意とする専門家にご相談されることをおすすめします。
なぜなら、遺言書は、書き方や内容に問題があると遺言書自体が無効になる場合や、遺言書が原因でトラブルになってしまう場合などがあるためです。
また、遺言書の書き方次第では、納める相続税額を抑えることに繋がるためです。
専門家の中には、あまり遺言書の作成に詳しくない方もいらっしゃいます。
実際、専門家が作成された遺言書の中には、内容に不備があり、相続開始後、相続人同士で裁判になったケースや、遺言書自体が無効になったケースもあります。
そのため、遺言書の作成を相談する専門家については、遺言の作成を得意とする専門家に頼んだ方が安心です。
そこで、以下では、遺言の作成を得意とする門家について、ご説明します。
2 法律に詳しい専門家
遺言書は、法律上の要件が欠けていたり、内容に不備があったりすると、遺言書自体が無効になり、また、遺言書の内容が実現できなくなる可能性があります。
そのため、遺言書を相談する専門家については、まずは法律に詳しい方に相談することをおすすめします。
専門家のなかには、相続案件をほとんどしたことがない方や、遺言書の裁判の経験がない方、遺言書を数件しか作成されたことがない方もいらっしゃるかと思います。
そういった専門家にご相談してしまうと、遺言書を作成される方の気持ちに沿った内容のものができなかったり、相続開始後、遺言書が原因でトラブルになったりする場合もあります。
そうならないためにも、遺言書の作成を相談する専門家としては、相続の実務経験がある専門家がおすすめです。
3 税金にも詳しい専門家
遺言書を作成する際は、法律だけでなく、税金についても気を付ける必要があります。
なぜなら、遺言書の書き方次第で、納める相続税額が異なる場合があるためです。
また、相続した土地を売却する際に発生する譲渡所得税についても、誰が土地を相続するかで、納税する金額が異なる場合があります。
そのため、遺言書の作成を相談する場合は、税金にも詳しい専門家にご相談されることをおすすめします。
4 弁護士と税理士がいる事務所がおすすめ
このように、遺言書の作成を相談する場合は、法律に詳しく、かつ、税にも精通している方がおすすめです。
たとえば、法律に詳しい専門家としては、弁護士があげられます。
また、税金に精通している専門家としては、税理士があげられます。
そのため、弁護士と税理士が連携しており、遺言書作成の際に、法律だけでなく、税金についてもご相談できる事務所にご相談されるとよいかと思います。
遺言作成を専門家に相談すべきケース
1 遺言の作成には注意点が多い

遺言の作成には、いろいろな気を付ける点があり、注意しないと遺言書が無効になったり、遺言の内容が原因で相続人同士がもめる事態になったりします。
そこで、遺言作成を専門家に相談すべきケースについてご紹介します。
なお、当法人も含めて、専門家による遺言の作成に関する相談について、無料で行っているところもありますので、お気軽にご相談ください。
2 手書きの遺言書を作成する場合
遺言書は、一つでも要件が欠けてしまうと、無効になる場合があります。
たとえば、手書きの遺言書の場合、作成日を「令和5年5月吉日」とだけ書き、具体的な日時を書いていないと、遺言書自体が無効になります。
また、遺産目録を除く、全文を手書きしなければならず、一部を作成者以外の人が書いてしまったり、一部をパソコンで印字したりすると、遺言書自体が無効になります。
このように、手書きの遺言書(自筆証書遺言といいます)の作成には、さまざまな落とし穴があります。
そのため、自筆証書遺言を作成する際は、一度、専門家にご相談されることをおすすめします。
3 財産のなかに不動産が含まれる場合
財産の中に不動産が含まれている場合、遺言の内容に問題があると、名義変更の手続き(登記手続き)ができなくなったり、手続きが複雑になったりする可能性があります。
たとえば、遺言書に未登記の建物が記載されていない場合があります。
この場合、未登記の建物部分をめぐって、相続人間で話し合いをする必要があります。
また、専門家であっても見落す点として、自宅の前の私道(道路)部分を遺言書に記載していないことがあります。
この場合、私道部分が遺言の効力から外れて、私道部分に関して相続人間で争いになることがあります。
このように、財産に不動産が含まれている場合、遺言の内容は重要であり、相続開始後に問題が生じないように注意が必要です。
4 財産の額が3000万円を超える場合
自宅や預貯金等の財産の額が3000万円を超える場合、相続税がかかる場合があります。
そして、遺言の書き方次第では、相続税額を0円にすることや、相続税額を大幅に減額できる場合があります。
たとえば、父と長男が同居しており、父が遺言で、長男に自宅を相続させた場合、特例を使えば、相続税の計算において、自宅の土地の価格が最大80%減額できる場合があります。
評価額が3000万円の土地の場合、600万円と評価されることになります。
その結果、相続税額を減額することが可能です。
他方、父が同居していない相続人に遺言で、自宅を相続させた場合、特例を使うことができず、高い相続税を支払う必要が生じる場合もあります。
このように、遺言の書き方次第では、相続税額を0円にすることや、相続税額を減額することができます。
もっとも、相続税も計算して遺言を作成することは、相続税を専門に勉強されている方以外は、なかなか難しい場合が多いです。
そのため、財産の額が3000万円を超える場合は、一度弁護士等の専門家にご相談されることをおすすめします。
遺言書作成を依頼する専門家の選び方
1 遺言書作成は専門家選びが非常に重要

「専門家に作成してもらった遺言書の内容に問題があった」というご相談を受けることがあります。
せっかく作った遺言書に問題があり、遺言書が原因で裁判になってしまったケースもあります。
「専門家に作成してもらったのになぜ?」と思うかもしれません。
その理由は、専門家の中にも、相続に詳しい専門家と、相続にあまり詳しくない専門家がいるということにあります。
遺言書を作成する際は、予備的条項や遺留分、保険の活用、相続税、裁判実務の運用等、相続に関する様々な制度の理解が不可欠ですが、専門家であっても、必ずしもこれらの制度に詳しいわけではありません。
そのため、裁判実務や相続税等にあまり詳しくない専門家に依頼してしまうと、書式を張り付けただけの簡単な遺言書を作成されてしまい、相続開始後にトラブルになってしまうかもしれません。
そうならないためにも、遺言書作成を依頼する専門家は慎重に選ぶことをおすすめします。
2 専門家を選ぶポイントはトータルサポートをしてくれるか
依頼する専門家を選ぶ際のポイントとしては、遺言書作成はもちろんのこと、相続税や遺留分等も含めてトータルサポートを行ってくれるかどうかということが重要です。
遺言書は、作成しただけで終わりではなく、相続税対策や遺留分対策等が必要になるケースもあります。
また、反対に相続税や遺留分等のことを考えると、必然的に遺言書の内容も変わってきます
そのため、遺言書作成を専門家に依頼する場合は、遺言書作成について、実務的な知識があることはもちろん、相続税や遺留分等についてもトータルサポートを行っているところに依頼することをおすすめします。
3 トータルサポートを行っている事務所かの見極め方
ご依頼する専門家がトータルサポートを行っているかどうかについては、ホームページや広告等で確認することができます。
また、相談の際に、相続税等についても相談できるのか尋ねてみて、確認する方法もあります。
4 遺言のご依頼は弁護士法人心へ
当法人は、遺言を含む相続のお悩み全般をトータルサポートできる体制を整えております。
相続を得意としている弁護士がご相談をお伺いし、様々な観点から、より良い遺言を残すことができるようサポートさせていただきますので、どうぞご相談ください。
遺言を作るメリット、デメリット
1 遺言を作るかどうかでお悩みの方へ

「遺言書を作った方がいいのか分からない」というご相談をよく受けることがあります。
相続においては、多くのケースで遺言を作成しておいた方がよいといえます。
こちらでは、遺言を作成しようか迷っている方に向けて、遺言を作るメリット、デメリットをご紹介いたします。
2 遺言を作るメリット
⑴ 紛争予防
遺言を作成することで、相続人同士の紛争を予防することができます。
相続人同士の仲が悪い場合や、相続人同士は仲がいいが、相続人の配偶者とは仲が良くない場合、そもそも相続人同士が疎遠な場合などは、相続開始後に揉める可能性が高いです。
揉めた結果、裁判になり、解決までに何年もかかる場合もあります。
もちろん、遺言があれば、絶対に揉めないというわけではありません。
しかし、少なくとも遺言を作成しない場合よりも、遺言を作成した方が揉める可能性を減らすことができるようになります。
なぜなら、遺言があれば、基本的にはそれに従って遺産を分けることになるため、相続人同士で遺産の分け方を決める必要がなくなります。
つまり、仲が悪い相続人や疎遠な相続人と話し合いをする必要がなくなりますので、揉め事が起こる可能性を減らすことができるという理由です。
⑵ 相続人以外の人に遺産を渡すことができる
遺言を作成することによって、遺産を親戚や内縁の妻、知人などの、相続人以外の人に渡すことができます。
そのため、相続人以外の人に財産を渡したい場合は、遺言を作成する必要があります。
なお、相続人となる順位は決まっており、親族だからといって、相続人となるわけではありません。
例えば、子がいる場合は、兄弟姉妹は相続人ではないため、兄弟姉妹に遺産を渡したい場合は、遺言を書く必要があります。
⑶ 遺産の分け方を決めることができる
遺言を書くことによって、遺産の分け方を自由に決めることができます。
例えば、長女にはお世話になったから、遺産を多めに渡すということもできます。
他方、次男には、今まで金銭の援助をしてきたから、遺産は少なくするということも可能です。
このように、遺産の分け方に自分の意思を反映させるためには、遺言を作成する必要があります。
⑷ 相続開始後の手続きが簡単になる
遺言を作成することによって、遺産分割協議書の作成などが不要になり、相続開始後の手続きが簡単になります。
仮に、遺言がないと、遺産分割協議書の作成や相続人全員の印鑑登録証明書が必要になり、手続きが煩雑になる場合があります。
なお、遺言の中で、遺言執行者を弁護士等の専門家にしておくと、後の相続手続きを対応してもらうこともできるので、おすすめです。
3 遺言を作るデメリット
⑴ 費用がかかる
公正証書遺言を作成する場合は、公証人に支払う手数料が必要です。
⑵ 遺言の要件を満たさないと無効になる
遺言には、法律上の要件があり、これを満たしていないと遺言が無効になります。
せっかく作成した遺言が無効になってしまうと、そのことが原因で争いになってしまう可能性もあります。
そのため、遺言を作成する際は、弁護士に一度ご相談されてから作成されることをおすすめします。
4 遺言の作成をおすすめします
多くの相続に関する相談を受けていく中で、「遺言があれば相続人同士の紛争を防げたのに」と思う機会が数多くあります。
たとえば、遺言がなかったことにより、仲の良かった姉弟が絶縁状態になるまで相続で揉めてしまった事例などがありました。
このような悲惨な事態にならないためにも、遺言の作成をおすすめします。
どのように作成すれば分からない等ありましたら、弁護士にご相談ください。
当法人では、遺言に関する相談は、相談料が無料ですので、安心してご相談いただけます。
遺言を作成するうえでの注意点
1 形式的要件を満たしていない遺言は無効になります

例えば、全文がパソコンで書かれた遺言や、日付のない遺言、押印していない遺言は、無効となります。
遺言が無効になると、相続人間で遺産の分け方について協議する必要があります。
話し合いだけで遺産の分け方が決まらない場合は、裁判で解決しなければならなくなる可能性もあります。
また、せっかく遺言書を書いたにも関わらず、遺言者の意思を無視した遺産分割が行われるかもしれません。
そうならないためにも、法律の要件を満たした遺言を作成する必要があります。
2 認知症が進んだ時に書いた遺言は裁判のリスクも
認知症が進んだ段階で書いた遺言書については、後日、裁判を起こされ無効となってしまう可能性があります。
実際、自筆証書遺言だけでなく、公正証書遺言を含めて、裁判でその効力が争われ、無効と判断されたケースが多々あります。
また、最終的に裁判で無効とならなかったとしても、裁判を起こされるだけで、かなりの時間と労力、費用が必要になります。
そのため、後日、裁判で争われないためにも、そして、争われた結果無効にならないためにも、遺言書については、早めに作成することをおすすめします。
また、認知症が進行していたとしても、すべての遺言が無効となるわけではないので、弁護士などの専門家の立ち合いのもと、公正証書遺言を作成することをおすすめします。
3 不平等な内容の遺言を作成する場合は、遺留分に注意
不平等な内容の遺言、例えば、一人の相続人にだけ全財産を渡すという内容の遺言については、後日、紛争が起こる可能性が高くなります。
例えば、子ども2人(兄弟)のうち、長男にだけ、全財産を渡した場合、財産を渡されなかった次男は、全財産を渡された長男に対し、全財産の4分の1の額を請求することができます。
これを、遺留分侵害額請求といいます。
4 遺言執行者を指定していない遺言書
遺言書は、その内容を実現して始めて意味を持ちます。
通常、遺言執行者と呼ばれる人が遺言書の内容を実現しますが、遺言執行者は、遺言書で指定することができます。
遺言執行者を指定しておかないと、裁判所で遺言執行者を選ぶ手続きを行う等、余計な期間や費用が発生します。
そのため、遺言書を作成する際は、遺言執行者もあわせて決めておくことをおすすめします。