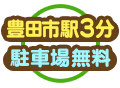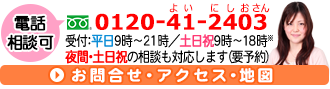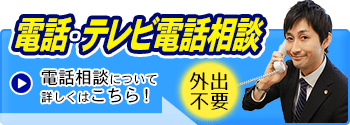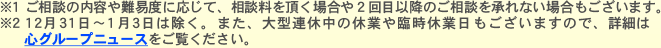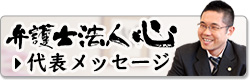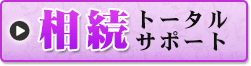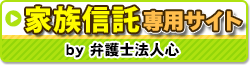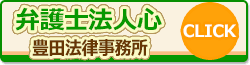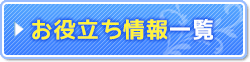遺言執行者の資格
1 遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言を作成された方が亡くなった後、遺言に記載された内容を実現していく人のことをいいます。
遺言執行者が遺言書の中で指定されている場合は、その方が遺言書の内容を実現する手続きを行います。
具体的には、遺言執行者は、遺言の内容に従って、自宅や土地、預貯金や株、投資信託等の遺産の名義の変更を行います。
相続人全員が手続に協力してくれる場合は、遺言執行者がいなくても、名義変更が行えます。
反対に、相続人が協力してくれない場合は、遺言執行者を指定しておかないと、自宅や預貯金、株、投資信託等の名義変更が行えなくなる場合があります。
2 遺言執行者の資格
⑴ 未成年者と破産者は遺言執行者になれない
遺言執行者は、誰でもなれるわけではありません。
具体的には、未成年者と破産者は、遺言執行者となることができません。
もっとも、相続人や遺産を受け取る人であっても、未成年者や破産者でなければ、遺言執行者となることが可能です。
また、弁護士や司法書士も遺言執行者となることができます。
⑵ 遺言執行者はもめごとにまきこまれやすい
遺言執行者は、遺言の内容に従って権利を実現しなければならず、遺言書で財産を得られなかった相続人との間で、もめごとになることが多々あります。
たとえば、「この遺言書の内容がおかしいから、こちらにも財産を分けろ」や「遺言執行者として法的義務を行っていないため、損害賠償を請求する」といったことを言われる場合もあります。
そのため、相続人ともめることが予想される場合には、弁護士などの専門家を遺言執行者として指定した方が安心でしょう。
⑶ 遺言執行者と指定されている場合でも代理は可能
遺言書で遺言執行者と指定されている場合であっても、遺言執行業務を弁護士に依頼して、代わりに行ってもらうことができます。
「相続人から文句を言われるのが怖い」、「遺言執行を全て自分でできるのか心配」という方は、一度、弁護士にご相談ください。
また、遺言書で遺言執行者として指定されている場合であっても、遺言執行者を引き受けないことが可能です。
そのため、遺言執行者として業務をしたくない場合は、相続人のうちの一人に、「遺言執行者の就任を拒絶します」と書面で伝えれば、遺言執行者にならずに済みます。
3 遺言執行者が遺言書で指定されていない場合
遺言書で遺言執行者が指定されていない場合、裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。
この場合、一般的には、遺言執行者として専門家が選ばれます。
なお、遺言執行者の報酬は、裁判所が決めることになり、通常、遺産額が多ければ、その分報酬も多くなります。
4 遺言執行者の業務内容
遺言執行者は、遺言の内容を実現することになりますが、その業務内容は法律で定められています。
業務の中には、行わないと、相続人から損害賠償の請求をされるものもありますので、注意が必要です。
この業務は、弁護士や司法書士だけでなく、相続人や親族が遺言執行者となっていた場合でも、その責任は同じです。
具体的に、遺言執行者は、以下の業務を行う必要があります。
①相続人や遺産を受け取る人への就任の通知
②財産目録の作成
③財産目録の相続人への交付
④名義変更手続き
⑤相続人への業務終了通知
遺言執行者の業務で非常に難しいのが相続人との対立です。
万一、遺言に不満を持つ相続人が、勝手に遺産に処分しようとしている場合、遺言執行者は、その相続人を止める義務があります。
5 遺言執行者で困った時は専門家にご相談
このように、遺言執行者の業務内容は様々であり、遺言執行者は、相続人同士のもめごとにまきこまれる可能性もあります。
そのため、遺言執行者が困らないためにも、遺言書を作成する場合は、遺言執行者を弁護士等の専門家にしておくことをおすすめします。
また、すでに遺言執行者になっている場合であっても、どのようにすれば分からない場合は、一度、専門家にご相談ください。